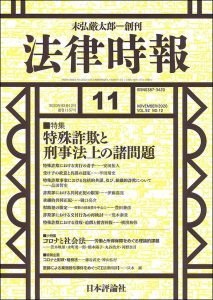医師による薬物投与事件をめぐって(只木誠)
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」92巻12号(2020年11月号)に掲載されているものです。◆
1 はじめに
我が国においては、終末期(人生の最終段階)にある患者本人が自らの意思に基づく行動をもって安楽死を迎える事案が法律上議論を呼ぶ事態となることは、例外的である。犯罪としての成否が問題となるのは、一般には、むしろ、家族等周囲の者が患者本人の死の意思の実現を手助けする場合、さらには、医師、看護師等、患者の医療に関わる立場にある者が死の床にある患者に対して安楽死を実施する事例においてである1)。
去る8月13日、難病のALSを患う京都の女性患者の依頼に応じた2名の医師が、薬物の投与をもって彼女を死に至らしめたとして、逮捕・起訴された。事件の詳細は今後明らかとなって行くであろうが、二人はいずれも当該女性患者の主治医を務めていたものではなく、女性とはSNS上で知り合い、事件当日まで面識もなかったようであり、事件の前に当事者間で報酬とおぼしき金銭の授受があったことが確認されていることなどから、本事件は、これまでに裁判において問題となってきた過去の安楽死・尊厳死の実施のケースとは状況が異なっており、また、そもそも、1991年に起きた東海大学安楽死事件で示された安楽死の許容される4要件からも逸脱しており、嘱託殺人にあたるとされるべき事案であるというのがおおかたの見解であろう。日本医師会も、今回の事件を受けて、「医の倫理に照らす以前に一般的な社会的規範を大きく逸脱し」た行為であるとの見解を発表している。むしろ、本事件であらためてクローズアップされたのは、その許容の如何という観点よりは、難病に苦しむ患者へ行う医療の在り方、患者が「死」ではなくなおも「生きる」ことを望み選択する環境をいかに保障することが出来るかという問題であるように思われる。
脚注
| 1. | ↑ | 裁判例としてはこれまでに8件確認され、そのうちすべてが有罪となり、すべてに執行猶予が付されている。なお、本稿で扱った問題については、只木誠・GunnerDuttge編『終末期医療、安楽死、尊厳死に関する総合的研究』(日本比較法研究所、近刊)参照。 |