(第1回)紛争・自然災害を経験して
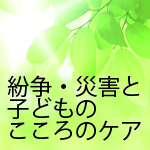 2022年ロシアによるウクライナ侵攻は日本に住む私たちにも大きな衝撃を与えました。また、新型コロナウイルスのパンデミックや自然災害など、私たちの日常を一変させる出来事がいつやってくるかは予想もつきません。こういった出来事はすべての人々のこころに暗い影を落としますが、特に子どものこころへの影響は計り知れません。この連載では、世界と日本の現場から、子どもたちのこころの健康を保つためにどんなことがされているのか、レポートしていきます。
2022年ロシアによるウクライナ侵攻は日本に住む私たちにも大きな衝撃を与えました。また、新型コロナウイルスのパンデミックや自然災害など、私たちの日常を一変させる出来事がいつやってくるかは予想もつきません。こういった出来事はすべての人々のこころに暗い影を落としますが、特に子どものこころへの影響は計り知れません。この連載では、世界と日本の現場から、子どもたちのこころの健康を保つためにどんなことがされているのか、レポートしていきます。(毎月上旬更新予定)
紛争や自然災害はテレビの画面越しの世界で起こっていることであり、自分の人生とはおよそ関係ないものだと思っていました。そもそも、こういった人生を揺るがすような出来事について真剣に考えたことすらありませんでした。私だけでなく、多くの人々が同じように考えているのではないでしょうか。毎日、起こるかどうかわからない戦争や大地震の心配をしながら暮らしていては、疲れ果ててしまいます。平和な一日が明日も続いていくだろうと考えるのは自然なことであり、私たちのこころの健康を保つ効果もあります。しかし、これまでの研究結果は、残酷な事実を私たちに突きつけます。世界人口の約7割が、一生涯に一度は災害、戦争、暴力事件、事故、性被害などのトラウマ的出来事を経験すると言われています。また残念ながら、日本は安全な国だからと安心することはできません。国内の調査でも、約6割の人々がトラウマ体験をもっていることがわかっています。トラウマ体験は、日々のストレスフルな出来事とは明瞭に区別され、人間の存在を脅かすような圧倒的体験と言えます。
生と死の境目がごく身近にあることを私が感じたのは、1995年の阪神・淡路大震災でした。当時私は大学入試をひかえた受験生で、一人暮らしをしていた大阪で被災しました。早朝、これまで経験したことのない揺れを感じて飛び起き、近くの公園に慌てて避難したことを覚えています。その後、入試の出願に必要な書類を母校から受け取るため、発災後間もない神戸の街を、途切れた鉄道、代替えバス、徒歩を駆使して通過しました。途中倒壊した家屋のがれきがそのままに残っており、まだそこに生き埋めになった人々がいるのではないかという思いにとらわれました。
後日、同じように被災した友人と会い、地震の体験を話す機会がありました。彼は、たまたまその夜はいつもと違う場所で眠っていたため、家具の下敷きになるのを免れたと言っていました。もし、いつもと同じベッドで休んでいたら、死んでいたかもしれない、と。こういった体験をしたからといって、私やその友人がこころに深い傷を負い、その後震災の記憶に苦しめられたというわけではありません。ですが、震災を生き延びることができたのも、こころに傷を負うことがなかったのも、たまたま運がよかっただけに過ぎないのかもしれません。
その後、大学で医学を学び、内科医として働きはじめて3年が経ったころ、勤務先の病院の近くにある国際医療NGOの事務所を訪れる機会がありました。阪神・淡路大震災を経験し、当時学生の身分で何もできなかったから、紛争や災害の人道支援に関わりたいと思ったというわけではありませんが、不思議と導かれるように海外での医療活動に参加しようと決心しました。そして派遣された場所は、ジョージアという国のアブハジア自治共和国でした。
アブハジアは、旧ソビエト連邦の崩壊に伴い、ジョージアからの分離独立運動が活発化し、1992年からジョージアとの間で紛争へと突入しました。その過程で約1万人が命を落とし、約30万人の難民が生じたと考えられています。1994年には停戦合意が成立し、国連およびロシアの平和維持軍が停戦の監視に当たっています。私は、そこに結核プロジェクトを担当する内科医として赴任しました。日々の業務は、入院患者の診察、現地医師との症例検討、病院管理上の問題対応などでした。重症の結核性髄膜炎患者の治療方針から、薬剤の管理、病棟のテレビや暖房器具の故障まで、ありとあらゆる大小さまざまな問題が毎日起こりました。ですが、全体的には多くの人々が想像する紛争地の医療活動よりはだいぶん落ち着いていました。毎日患者さんが亡くなっていくことはありませんし、銃声や砲弾が飛び交うといったこともありません。
表面上の平穏とは裏腹に、日が経ち、現場を理解するにつれて、ある種のストレスを感じるようになりました。例えば、当時の国際基準に準じたベストの結核治療を提供しているにもかかわらず、必ずしも患者さんたちが満足しているわけではないということに気づきました。時に患者さんが治療から脱落していくのを止められないこともありました。文化、国民性の違いもひとつの要因だったかもしれません。家族、親戚の冠婚葬祭だと言って1、2週間治療を中断するのは当たり前でした。さらに、30~40代の男性患者さんを中心として治療に対する無気力さを感じることもありました。翻って考えると、この世代は10年前の戦争を最も身近で体験した世代であり、戦争体験が長年にわたって彼らのこころに悪影響を与えていたのかもしれません。実際、阪神・淡路大震災から20年を経て兵庫に戻り被災者のケアを行うようになり、トラウマ体験がいかに根深く、しかも長きにわたり人々を苦しめるかを実感することとなります。
兵庫県こころのケアセンターは、阪神・淡路大震災の被災者の心理的支援を担ってきた組織が発展してできた全国で初のトラウマや心的外傷後ストレス障害(PTSD)の研究機関です。その付属診療所では、トラウマとPTSDに特化した専門外来治療を提供しています。ここで私も、患者さんを担当する医師として心理療法を中心としたトラウマ治療を実践してきました。私がこのセンターに着任したのは、前述の通り震災から20年近く経ってからであったため、阪神・淡路大震災の被災を主な悩みとして来所されている方は決して多くはありませんでした。紛争や災害などを体験したからといって、全員がこころに傷を負うわけではありません。また、傷ついた人々の多くは、身体の傷と同様に、環境が整えば自然と回復していきます。20年も経てば、こころの傷痕は全体としては目立たなくなります。しかし、長年にわたり苦しみを抱えながらもなんとか日常生活を営んでいる方々がおられます。
例えば、被災体験が、間接的なこころの症状として現れる場合があります。ある男性は、長年パニック発作に苦しめられて、車や電車に乗れなくなっていました。パニック発作は、典型的には不安や恐怖を伴った胸の痛み、動悸、めまいが突然起こり、このまま死んでしまうのではないかと感じます。この発作は特定の状況で起こることが多く、この男性の場合は閉鎖された空間がきっかけとなっていました。一般にパニック発作はありふれたもので、トラウマとは関係なく、おおよそ10人に1人が体験しうると考えられています。通常は、内服治療や心理療法が奏功することが多いのですが、この方の場合、あまり効果は得られませんでした。そこで被災体験を紐解いていく中で、発災直後にドアや窓が地震で歪んで自室にしばらく閉じ込められたこと、その時に次の揺れが来れば生き埋めとなり、確実に死んでしまうのではないかと恐怖を感じたことが思い出されました。パニック発作の根底には、この被災体験が深く関係していたのです。したがって、震災のトラウマ体験を心理療法で適切に処理することで、パニック症状は劇的に改善しました。
被災体験は、必ずしも病的な症状として現れるわけではありません。ある被災者の方は、子どものころに震災を体験し、家族の一人を喪いました。そのため、両親がひどく精神的に落ち込み、家庭は暗い雰囲気が長く続いたそうです。両親をこれ以上心配させないために、自分は決して弱音を吐かないでおこうと誓ったそうです。そうやって思春期を過ごし成人した結果、人に悩みを相談したり、自分の気持ちを打ち明けたりすることができなくなってしまったとおっしゃっていました。
ここで紹介したケースは、私の臨床経験に基づく架空のものですが、実際トラウマ体験の影響は多様であり、一見すると周囲にはわかりにくいものが多いのです。そしてトラウマ体験は、遠い国の知らない誰かに起こる不幸ではなく、すべての人々の人生と背中合わせになっています。日本と世界でこころにつらい傷を負った方にいったい何ができるのか、この連載を通して私自身が皆さんとともに考えていきたいと思います。
◆この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。
この連載をすべて見る
 田中英三郎(たなか・えいざぶろう)
田中英三郎(たなか・えいざぶろう)2001年愛媛大学医学部を卒業、精神科医師。ユニバーシティカレッジロンドン(UCL)等で社会疫学を研究、公衆衛生学修士、博士(医学)。国立国際医療研究センター、国境なき医師団、都立梅ヶ丘病院、兵庫県こころのケアセンター等を経て、2021年よりJICAヨルダン事務所・ヨルダン保健省精神保健政策アドバイザーを務めている。





