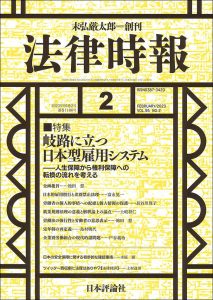ツイッター買収劇に法理はありや?(上村達男)
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」95巻2号(2023年2月号)に掲載されているものです。◆
1 全株の所有者、イコール「企業の」所有者か
自動車会社テスラの経営者として成功を収め大富豪となったイーロン・マスク氏が、ツイッター社の全株式を所有したことをもって、マスコミではマスク氏がツイッターの所有権を握ったといったことが言われている。しかし、マスク氏はツイッターの全株式を所有しただけであって、ツイッター社を所有したわけではない。この違いを認識しない論調が日本のマスコミに多いのは、この30数年でアメリカ同様の「会社は株主のもの」という発想に浸り、感覚が麻痺しているからだろう。全株持ったからには会社の事業目的が何であっても何でもできる、という発想はカネがあれば何でもできると言っているに等しいのだが、マスク氏は全株式の購入代金(440億ドル――6兆円超)の全額を自前で賄ったわけではなく、約3分の1はモルガンスタンレーなど金融機関からの借り入れとされ、その際の担保はツイッター社の資産と将来キャッシュフローだという。さもありなん。
3分の1の借り入れとはいえ、その金額は2兆円にもなる。この構図は借金による企業買収LBO(leveraged buy out)そのものである。1980年代のアメリカで、金づくの借金漬け買収ないしジャンクボンド(低格付けぼろくず社債――アメリカ人が「ぼろくず:junk」と呼ぶものを日本人はこれをハイリスク・ハイリターン金融商品と美名?で呼んだ)の発行による企業買収の横行が、対象企業の切り売り、企業が提供する商品・サービスが提供されないことによる地域住民・地域社会の衰退、インサイダー取引・相場操縦の横行等に繋がるとの認識が一気に拡がった。株式市場は「正しいものを勝たせない」との認識が、コーポレート・ガバナンスの意義の重視に繋がったという経緯がある。
借金漬け買収は要は買収対象企業の資産・将来キャッシュフローを担保に取る取引であるから、買収が成功した暁に待っているのは借金を返すための買収企業資産の切り売りないし従業員の解雇であり、もろもろの安全装置の弱体化等である。これについては、対象企業がバラバラになっても対価が公正なら何も変わらないのだから正しい取引だと公言する反社会的な経済学者や法律家たちが多数存在した。この発想こそが、企業を組織として人格ある人間の集合体と見ずに、個々の取引の集合体(契約の束)とし、契約コスト・代理コストの最小化による効率経営こそが企業論の至上命題であるとする法と経済学(Law and Econmics)の流行と結びつき、制度の劣化を著しく進行させた。こうした一神教はもともと欧州の法の歴史や思想等の素養を受け継いでいないアメリカで、あたかもそれが規範を論ずべき法律学であるかに普及し、日本の法学者にもその信者が一派を形成し、ひたすら規制緩和の意義を強調し続けた。欧州的経験知に基づく制度は現時点での効率の観点ないし実証研究の不在を理由にその存在理由が簡単に否定された。
短期借金漬け買収でなくても、自前の資金であってもこうした行為は許されないが、借金漬け買収は悲惨な結果を予め確実に予想できる取引であるところに強い違法性を想定してきたのである。
買収後現実に、ツイッター社の経費削減のために投稿管理部門が大幅に縮小され、従業員の75%が解雇されたという。マスク氏はCEOに就任すると同時に9人の取締役全員を解任し、取締役1人となってこうしたことを断行したとされる。2億人とも4億人とも言われる利用者を擁し、3000社ほどの広告主を有しSNSの世界に君臨するツイッター社の株主が一人、取締役が一人となった。こうなると何でもできるとばかりに、自分に批判的な人物のアカウントを凍結したり、永久追放とされたトランプ氏のアカウントを復活するなど事業活動の個々の事案について自分の意向を直接反映させる挙に出た。
全額個人出資の個人商人なら無限責任を負う。親会社が1名の100%子会社でも取締役会などガバナンスの充実がなければ、あるいはあっても有限責任のはずの完全支配親会社が全面的な責任を負うのが常識である。アメリカには支配株主の会社に対する忠実義務、取締役の対会社責任も存在するはずであるが、6兆円という資金を前に、訴訟をしようとする者はほぼおらず、裁判官も金額に委縮するというのが通例である。