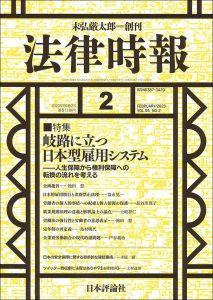(第54回)労働法における自由意思論(合理的意思論)(松井博昭)
 企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。
企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。(毎月中旬更新予定)
池田悠「労働法の強行性と労働者の意思表示」
法律時報95巻2号(2023年)29頁
1 契約に関する基本概念として、契約自由の原則(私的自治の原則)があり、契約締結、契約内容の決定に当たっては個人の意思が尊重される。ところが、労働法には当事者の意思に反しても適用されるという強行法規性があり、また、雇用に関する合意についても、合意の内容や存在自体が裁判所により否定されるという事例も存在する。
池田悠「労働法の強行性と労働者の意思表示」は、こうした労働法の強行法規性と自由意思論(合理的意思論)を分析した、実務上も参考となる論文である。
2 「自由意思論」とは、労働者の意思表示については、たとえ、明確に書面化されており、かつ、労働者が当該意思表示の意味を理解しているように見えるとしても、自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在しない場合、当該意思表示が無効とされ得るとする考え方であり(和田肇「山梨県民信用組合事件最高裁判決のその後」季刊労働法270号(2020年)40頁等)、最二小判平成28年2月19日民集70巻2号123頁(山梨県民信用組合事件)を契機に広がりを見せているとされる。
これは過去の最高裁判例で、賃金債権放棄の意思表示(最二小判昭和48年1月19日民集27巻1号27頁(シンガー・ソーイング・メシーン事件))、相殺合意の意思表示(最二小判平成2年11月26日民集44巻8号1085頁(日新製鋼事件))に適用した判断枠組みを、就業規則変更による退職金減額にかかる労働者の同意にも適用したものである。
しかし、前掲・山梨県民信用組合事件は、その根拠として「労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があること」を挙げるのみで、必ずしも適用範囲が明らかではない。
本稿は、この「自由意思論」と呼ばれる判断枠組みは、労働者の意思表示について、自由な意思に基づくか否かに関心を持つものではなく、客観的合理性を要求するところにその趣旨が認められるとして、本来「合理的意思論」と表現されるべきものであると指摘している。
3(1) その上で、本稿は、労基法との関係も踏まえ、適用され得る領域について検討している。すなわち、雇用契約においては、元来、私的自治の原則が及び、民法上の強行法規に抵触する場合にのみ例外的に制約を受けるにすぎなかったが、昭和22年、当事者自治を一律に排除する強行的直律的効力(13条)を持つ労基法が導入され、当事者の自治に委ねられた領域は縮減されることになった。
その結果、当事者の意思に委ねられた領域として残されたものは、第1に、労基法で規制されていない(いわゆる広義の)労働契約法の領域、第2に、関連する現象の規制自体は存在するもののなお強行法規による規制の対象外と解釈される領域であり、「合理的意思論」が及び得るのもこれらの領域とされる。
(2) まず、第1の(いわゆる広義の)労働契約法の領域について、労基法施行後、解雇権濫用法理、(他律的な労働条件設定の一般化を認める)就業規則法理等の確立により、労働者の意思表示を媒介しない領域が更に増え、当事者自治に委ねられる労働契約法の領域として残されたのは、(a)労働契約の成立、(b)労働者の意思を介在させた労働契約の終了(辞職・合意解約)、(c)就業規則法理による規律が及ばない事項に限られている。
(a)労働契約の成立について、諾成契約という性質上、意識されること自体少なかったが、近時は、法律上の権利を放棄する意思表示の有効性を判断する裁判例もある。ただし、(b)労働契約の終了について、本稿は、「合理的意思論」は、労働者の辞職及び合意解約にかかる意思表示に妥当するものとは解されていないとする。
(c)就業規則法理による規律が及ばない事項のうち、職種(一般職・総合職などのコース選択を含む)・勤務地・期間の定めについて、本稿は、賃金と並ぶ重要な労働条件として、労働者の意思表示に「合理的意思論」を当てはめる傾向が顕著であるとする(宇都宮地決令和2年12月10日労判1240号23頁(学校法人国際医療福祉大学(仮処分)事件)等)。
(3) 次に、第2の労基法による規制の対象外と解釈されてきた領域として、本稿は、(a)研修・留学費用の返還合意、(b)相殺合意や相殺への同意を挙げる。
(a)研修・留学費用について、本稿は、費用返還合意について労働契約とは別個の金銭消費貸借契約が成立している場合、労基法16条が禁止する違約金の約定や損害賠償の予定には該当しないものと判断されているが(東京地判平成9年5月26日労判717号14頁(長谷工コーポレーション事件)等)、その判断において、労働者の意思表示につき客観的合理性を要求する「合理的意思論」に類似する解釈がとられていると指摘する。
(b)相殺合意や相殺への同意について、本稿は、前掲・日新製鋼事件以降、「合理的意思論」の下、労基法24条1項に違反しないと判断されているとする。
4 このように「合理的意思論」には2つの系統があり、1つ目は、もともと強行法規による規制の対象外で当事者自治に委ねられる事項ではあるものの、関係する強行法規の趣旨を没却することがないように設定される「合理的意思論」であり、2つ目は、一定の範囲でのみ合意の優先を許容する労契法の半強行法規との関係で、当該合意や同意の是非を判断するために設定される「合理的意思論」である。
これまで「合理的意思論」については、必ずしも根拠が明確でない状況の下、適用対象の確定が難しいという印象があった。
本稿が指摘するとおり、今後は、両者の趣旨の違いを踏まえつつ、その関係をめぐる理解を精緻化し、それぞれの「合理的意思論」の趣旨に適合した適用範囲を画していく必要があると思われる。
本論考を読むには
・法律時報92巻2号(1186号) 購入ページへ
◇この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。
この連載をすべて見る
 松井博昭(まつい・ひろあき)
松井博昭(まつい・ひろあき)AI-EI法律事務所 パートナー 弁護士(日本・NY州)。信州大学特任教授、日本労働法学会員、日中法律家交流協会理事。早稲田大学、ペンシルベニア大学ロースクール 卒業。
『和文・英文対照モデル就業規則 第3版』(中央経済社、2019年)、『アジア進出・撤退の労務』(中央経済社、2017年)の編著者、『コロナの憲法学』(弘文堂、2021年)、『企業労働法実務相談』(商事法務、2019年)、『働き方改革とこれからの時代の労働法 第2版』(商事法務、2021年)の共著者を担当。