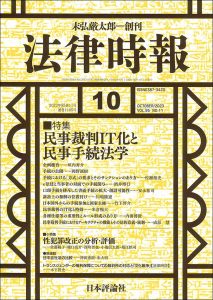トランスジェンダーの権利保障についての裁判所の対応と「文化戦争」(木下智史)
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」95巻11号(2023年10月号)に掲載されているものです。◆
1 経済産業省職員事件最高裁判決
最高裁判所第三小法廷は、去る7月11日、「性同一性障害」(以下では「性別違和」の語を用いる)の診断を受けている経済産業省職員(Aさんと呼ぼう)が職場のトイレ使用に関して求めた行政処置を拒否した人事院の処分の違法性を認める判決を下した(裁判所ウェブサイト)。
まずは、簡単に事実関係を振り返っておこう。
経済産業省に勤務するAさんが自身の性別違和について「性同一性障害」の診断を受け、職場でも女性として勤務することを希望するようになり、上司に、女性としての服装や女性トイレの利用等について相談したのは2009年7月。同省秘書課調査官が対応を検討し、2010年6月になって、Aさんが女性の服装で勤務することを認め、トイレ使用についてはAさんの性別違和についての「説明会」(職場の同僚62人が参加)を経た後、女性職員の意見聴取を踏まえて判断するとの対応方針を決定した。「説明会」では表だって異論は出なかったものの、女性トイレの使用について「数名の女性職員がその態度から違和感を抱いているように見えた」ため、執務階とその上下階の女子トイレの使用を認めず、それ以外の階の女子トイレの使用を認める処遇を行った(以下「本件処遇」という)。
Aさんは2011年に名も変更し、女性として生きていく姿勢をより明確としたが、アレルギー症状のため、性別適合手術を受けることが困難であり、戸籍上の性別は男のままであった。やがて、Aさんは抑うつ状態に陥り、休職を余儀なくされた。再び出勤できるようになった後も、本件処遇に変わりがなかったため、2013年12月、人事院に対して国家公務員法86条に基づく行政措置によって、女性トイレ使用に関する制限を撤廃する等の行政措置を要求したが、2015年5月29日付けで当該措置要求は認められない旨の判定(以下「本件判定」という)を受けた。
第一審判決(東京地判2019年12月12日判時2528号32頁)は、経産省は、性的な危害を加える可能性を含め、Aさんの女性トイレ使用によりトラブルが生ずる可能性が「せいぜい抽象的なものにとどまるもの」であることを認識することができたと認定し、本件処遇が、遅くとも2014年4月7日(Aさんの職場復帰の日)の時点においてAさんの「性自認に即した社会生活を送るといった重要な法的利益等に関する制約として正当化することができない状態に至っていた」と判断し、本件判定の取消しと国家賠償請求を認容した。しかし、控訴審判決(東京高判2021年5月27日判時2528号16頁)は、人事院による行政措置要求の判定の司法審査について、人事院の行政措置の範囲とそれに対する司法審査の範囲とを著しく限定する枠組みを用い(この基準の問題については、岡田正則「職場での性自認の尊重と人事院・裁判所の責任」法時93巻12号4頁以下参照)、本件判定の違法性を否定する判断を示した。
これに対して、最高裁は、国公法86条に基づく行政措置要求についての人事院の判断について、「広範にわたる職員の勤務条件について、一般国民及び関係者の公平並びに職員の能率の発揮及び増進という見地から、人事行政や勤務等の実情に即した専門的な判断が求められる」ものであることを認めた上で、本件判定が裁量権の逸脱・濫用にあたると判示した。最高裁は、Aさんが執務階のトイレを利用できないことにより「日常的に相応の不利益を受けている」ことを認め、他方で、「遅くとも本件判定時においては、上告人が本件庁舎内の女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかったのであり、上告人に対し、本件処遇による上記の不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったというべきであ」り、本件判定部分に係る人事院の判断は、「本件における具体的な事情を踏まえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し、上告人の不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びに上告人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして、著しく妥当性を欠いたものといわざるを得ない。」と判示した。この判断は、人事院が職員の勤務条件について専門的な判断を行う責任を有する機関であるとの認識を踏まえ、その判断過程が厳密に審査されるとの見地に基づくものである。
本判決は、第三小法廷のすべての裁判官が補足意見を述べるという異例の判決となった。それぞれの意見からは、法廷意見には表れなかった本件判定の不合理さを示す事情が浮かび上がってくる。宇賀裁判官は、Aさんによる女性トイレ使用に対する女性職員の違和感・羞恥心等は、トランスジェンダーに関する研修によって払拭すべきものであることを指摘した。渡邊裁判官は、「説明会」において女性職員が違和感を抱いているように「見えた」ことについて考察し、実際には、Aさんの女性トイレ利用を容認する趣旨で異議を述べなかった職員ややむを得ないと考えた職員もいたことを指摘し、原判決がこうした多様な反応を考慮せず、「性的羞恥心や性的不安などの性的利益」を根拠に、本件処遇の合理性を承認したことを批判した(立石結夏「トランスジェンダー女性問題から見える社会の歪み――経済産業省職員事件」法セ824号〔2023年〕60頁以下、65頁)。
Aさんは、最終的に最高裁で勝利したものの、Aさんが最初に声をあげてから最高裁がその主張を認めるまで14年の歳月が経過している。そして、その間にAさんが辿った道のりは過酷なものであった。女性トイレの使用を認めてもらうために60人以上の職員の前で自らの性的違和について説明を強要された挙げ句、結局は職場から離れたトイレの使用しか許されなかった。過敏性腸症候群を発症したAさんには、離れたトイレに行かなければならないこと自体が苦痛を伴う。本件処遇後は、上司や調査官との「面接」において、繰り返し性別適合手術を受けて戸籍を変えるよう促され、異動先で女性トイレを使用するためには、その都度、「説明会」を開くよう求められ、時には、「手術を受けないんだったら、もう男に戻ってはどうか。」などの暴言に晒されることもあった。Aさんが抑うつ状態に陥ったことも、こうした職場の状況と無関係ではないだろう。そして、カミング・アウトから4年10ヶ月が経っても、結局、トイレ使用の制限が改善される見込みがないと知ったときには絶望さえ感じたのではないだろうか。
今崎裁判官は補足意見のなかで、本件の事実関係を超えてトランスジェンダーのトイレ利用の問題の解決のために「今後事案の更なる積み重ねを通じて、標準的な扱いや指針、基準が形作られていくことに期待したい。」と将来に向けてのコンセンサス形成に期待を寄せた。一般論としては、確かにそうなのであろうが、「事案の更なる積み重ね」の過程で、Aさんが経験したような苦難が続くとすれば、やりきれない気がする。