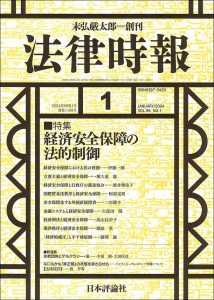なにもかも「非正規」の状態を終わらせる――イスラエル・パレスティナ問題について(西平等)
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」96巻1号(2024年1月号)に掲載されているものです。◆
1 非正規の戦争
パレスティナとイスラエルの関係をひとことで特徴づけるとすれば、それは「非正規(irregular)」だ。国際法の世界で「非正規の者たち(irregulars)」と言えば、非正規戦闘員のことを指す。すなわち、政治的な立場に応じて「ゲリラ」、「パルチザン」あるいは「テロリスト」などと呼ばれる、正規の戦闘員としての資格を持たない戦闘従事者のことである。ハマスを中心とするガザ地区の武装勢力は、非正規戦闘員として位置づけられる。
戦闘員資格を持たないということの最も重大な意味は、捕虜としての待遇を受けないということ、すなわち、(交戦法規の枠内で)戦闘に従事したことを理由として処罰されないという免責特権が認められないということである。18世紀から19世紀にかけて確立してゆくヨーロッパの国家間戦争概念の下では、戦争は、国家の権威の下に組織された正規軍同士によって戦われるべきものとみなされ、国家の命令の下で戦闘に従事する正規軍の構成員には捕虜としての待遇が認められた。捕虜は犯罪者ではない。したがって、捕虜を処罰してはならず、休戦が成立すれば速やかに解放されるべきである。戦争そのものが違法であるかどうか(例えば、侵略戦争であるかどうか)は、ここでは関係がない。違法な戦争もまた、組織犯罪ではなく戦争であり、そこでは交戦法規が平等に適用されるからである。もう少し論理的に説明するなら、国家行為としての戦争から兵士個人の責任を切断するのが免責特権の意味であるから、国家行為そのものが違法であったとしても、そこから個人の責任は切断されている(だからこそ侵略戦争を遂行した私たちの父祖も捕虜待遇を享受した)。
戦闘は人殺しであり、破壊なのだから、免責が認められなければ、戦闘従事者は刑法や軍法に基づいて処罰される。したがって、免責特権を持たない非正規戦闘員が捕まった場合、犯罪者として処罰される。ただ、国際法上、非正規戦闘員が禁止されているわけではない。非正規であるがゆえに国際法上の保護を受けないが、にもかかわらず、自らその危険を引き受けて戦闘に従事する者として位置づけられる(それゆえ国際法上は「違法戦闘員」という語は使用されない)。20世紀は非正規戦闘員の時代であり、外国勢力による占領地の解放や植民地の独立のために、パルチザンやゲリラが活躍した。彼ら彼女らは、大義のために自ら危険を引き受ける者として、英雄視されることもあった。今となっては遠い昔のことのように感じられるが、1970年代までの国際法は、非正規戦闘員を「テロリスト」として処罰することよりも、むしろ、非正規戦闘員に戦闘員資格と捕虜待遇を拡大することに注力していた(1907年ハーグ陸戦規則1条および2条、1949年ジュネーヴ捕虜条約4条A、1977年ジュネーヴ諸条約第一追加議定書1条4項など)。古い時代を扱った映画などでよく、捕らえられたゲリラが「われわれを戦闘員として扱え」と言っているのは、そのためである。
なぜ危険を引き受けて非正規戦闘員となるのか。それは、正規軍としては勝ち目がないからである。彼我の戦力差が歴然としている場合、正面からの衝突では簡単に打ち破られてしまう。したがって、敵の弱点を狙って小規模な軍事活動や破壊を繰り返し、相手を消耗させるという戦略が選択される。
しかし、非正規戦闘員による戦争はおぞましい状況を生む。軍事力に劣るゲリラは、発見されれば簡単に鎮圧されてしまう。だからどこかに隠れなければならない。ときには人の入り込まないジャングルに、ときには人であふれた街の中に、身を潜めることで相手の攻撃を避ける。そして、機を見計らって小規模の攻撃を仕掛ける。相手は、「見えない敵」に苛立ち、怯え、消耗する。しかし、このような戦略は、相手方の苛烈で残虐な反撃を招くことになる。優勢な軍事力を持つ側からすれば、姿をくらます卑劣な「テロリスト」どもを始末するために手段を選ばず徹底的に攻撃する、ということになってしまう。ジャングルに潜むならジャングルもろともに焼き払え。街に潜むなら街もろともに。
国際人道法の原則である「戦闘員」と「文民」の区別は、そもそも、国家間戦争を前提として、つまり、軍服を着た重装備の正規軍同士が戦場で勝敗を決するという想定の上に確立されてきた。ところが、ゲリラは、このゲームのルールを変えることで、軍事的に優勢な敵に負けないことを目指す。「戦闘員」と「文民」の区別から離れ、敵の兵士だけではなく、政治家、内通者、対敵協力者などを標的とする。一般市民そのものを狙ったテロ行為さえ生じる。軍事占領に深い恨みを抱く人々が、強い憎悪の下でテロを容認してゆく。しかし、テロはテロを生む。子供たちを爆殺するような残酷なテロリストどもを根絶するためには付随的な犠牲はやむを得ない、という論理が、子供たちを巻き込む空爆を正当化する。
国際人道法や国際刑事法の適用によってこの惨状を和らげることはできないのか。もちろん、できるだろう。しかし、限界がある。まず、国際法によって文民に対する空爆や砲撃を制止できるか。文民の保護は国際人道法上の基本原則である。しかし、交戦法規は「付随的損害」を認めており、軍事的な必要のために付随的に文民を巻き込むような攻撃を行うことを許す。それゆえ、極端な場合には、そこに敵の司令部があるといえば、病院を攻撃することも正当化されてしまうかもしれない。また、国際法によって非道なテロを阻止しうるか。それらテロ行為は(非国際武力紛争にも適用される)国際人道法の違反であろうし、その行為者を国際刑事法に基づいて処罰することもできないわけではない。しかし、免責特権を持たない非正規戦闘員は、正確に軍事目標のみを攻撃したとしても、それだけですでに犯罪者として扱われ、占領軍によって厳罰に処される。犯罪者として扱われるゲリラたちに、その犯罪行為を国際法の枠内で行えと要求することに、どれほどの意味があるだろうか。国際社会の介入に対する期待と信頼を保っているうちは、ゲリラも国際法を尊重するかもしれない。そうでないなら、遵守への動機づけはさしたるものでない。