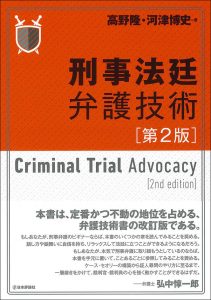『刑事法廷弁護技術[第2版]』(著:高野隆・河津博史)
第2版 はしがき
初版の刊行から6年余りが過ぎた。「オレンジ本」という愛称で刑事法廷技術の基本書として多くの読者を獲得できたことはわれわれにとって大きな喜びである。それとともに、直接主義・口頭主義の真価を理解し、「法廷こそが主戦場である」という意識を持った法律家――弁護士だけではなく、検察官を含む――が増えてきていることを実感している。最近の公判廷では、弁護人はもちろん、検察官のなかにも、法廷の中心に立って事実認定者の目を見て弁論をする人がいる。本書が推奨している証人尋問の技術を実践し、その効果を実感している法曹は確実に増えている。
しかし、良いことばかりではない。刑事裁判官のなかには、何もかも公判前に決めてしまおうと考えている人がいる。民事裁判の弁論準備のように、検察官の起訴状や証明予定事実の細目に対する弁護側の認否を明らかにさせ、公判での弁論や証言の役割をできるだけ少なくしようとする人がいる。弾劾尋問の典型である自己矛盾調書を呈示する尋問を、意味もなく、制限する裁判官も多い。そして、裁判官裁判だけでなく裁判員裁判においてすら、公判は連日開かれず、間延びした期日指定がなされることが増えているように感じる。公判廷で行われる口頭での立証活動は部分的なものとなり、事実認定者は、公判廷という一回性の空間で白紙の状態から一気に心証形成することが難しくなっている。記録や提出物に頼って――法廷の外で――心証形成をせざるを得なくなる。裁判員と裁判官の間の情報格差が広がり、裁判員は裁判官に頼らざるを得なくなる。こうなっては元の木阿弥である。
いかなる改革にも必ず抵抗がある。長年にわたって慣れ親しんだ方法を捨て去り新しい技術を身につけるのはたやすいことではない。裁判員裁判がはじまって15年が経過したが、「産みの苦しみ」はまだしばらく続くであろう。いまこのときこそわれわれは司法制度改革の初心に帰るべきである。直接主義・口頭主義の公判手続こそ、憲法と法に根ざした公正な裁判なのであり、すべての国民に開かれた刑事裁判を実現するものである。刑事裁判に携わるすべての法曹はこれを自覚し実現する責任を負っている。われわれが人間諸科学に基礎をおいた法廷技術を身に着けこれを実践することは、最善の防御を誓った依頼人への責務であると同時に、主権者たる国民から付託された使命でもある。この責務と使命を履行するために少しでも役に立つことを本書は目指している。
この版は初版の基礎にある理論をそのまま受け継ぎ発展させた。著者自身の法廷実践や研修での指導経験を通じて考えたこと、法と心理学に関する最近の知見などを踏まえて相当程度の加筆修正を施した。読者が実践的なイメージを容易に持てるように、設例やイラスト、書式例などもかなり増やした。その結果ページ数は大幅に増量した。
今回も日本評論社の武田彩さんには、編集者の枠を超えて貴重な意見や提案をいただき、また、怠け者の著者を叱咤激励していただいた。イラストレーターの高橋千文さんには、われわれの細かい注文を反映した新しいイラストを多数追加していただいた。お2人には最大の感謝を申し上げたい。
2024年5月
高野 隆
河津博史
初版 はしがき
2009年に施行された裁判員制度は、日本の刑事裁判に大きな変化をもたらした。それまで、刑事裁判における事実認定は、職業裁判官によって独占されていた。そこでは、直接主義・口頭主義の原則は、すっかり形骸化されていた。法廷は、捜査資料を中心とした証拠書類を受け渡し、当事者が書面を読み上げ、裁判官がそれを聞き置く場面と化していた。法廷が開かれるのは数週間に1度のペースであり、裁判官は数多くの事件を同時並行的に処理していた。実際の判断形成の心理的プロセスとは異なった、判決書における判決理由の書き方が「事実認定」と呼ばれ、その方法が教育され、裁判官の間で受け継がれてきた。
裁判員制度の施行により、事実認定は普通の市民が参加して行われるものとなった。証人尋問を中心とした証拠調べが行われ、当事者には、裁判員が法廷で聴いて理解することのできる弁論をすることが求められるようになった。裁判員は1つの事件だけを担当し、法廷は連日的に開かれるようになった。こうした変化は、裁判員制度対象事件以外の刑事裁判にも、徐々に影響を及ぼしつつあるが、その一方で、裁判員の参加する刑事裁判において旧来の刑事裁判と異なる結果が生じることに抵抗する力には、依然大きいものがある。日本の刑事裁判は、いまだ過渡期にあるとみるべきである。
筆者らは、裁判員法が成立した2004年以降、日本弁護士連合会裁判員制度実施本部(当時)のメンバーとして、裁判員制度に対応した法廷技術の研究をし、各地で開催された研修の講師を務めるなどしてきた。2006年には「自由と正義」に連載された「裁判員裁判と法廷弁護の技術」の執筆に参加した。2007年には「わが国初の体系的弁護技術書」である『法廷弁護技術』(日本弁護士連合会編)の初版が刊行され、2009年には第2版が刊行された。同書は、中国語版(『法庭辯護技術〔第2版〕』)も台湾で刊行されている。
本書は、それらの成果の上に立ちつつ、裁判員制度が施行された2009年以降の新しい刑事裁判の経験や国内外の各種の研究結果を踏まえ、新たに書き下ろした法廷技術の基本書である。法廷技術は、目標とする判決に事実認定者を導くための技術である。法廷で聴いて理解できる主張・立証をすることは、その必要条件であるが、十分条件ではない。目標とする判決に事実認定者を導くためには、裁判官の判決理由の書き方ではなく、事実認定者の判断形成の心理的プロセスに対応する必要がある。本書は、そのような立場から、法廷での立ち居振舞い、ケース・セオリーとケース・ストーリーの作り方、そして公判の各場面における弁護活動のあり方を解説するものである。
弁護人が法廷技術を修得することは、公正な刑事裁判を実現するための必要条件である。事実認定者の判断形成の心理的プロセスに関する研究は、事実認定者の信念や先入観が証拠の認知や記憶を歪め、判断を誤らせることを明らかにしている。効果的に証拠を見聴きさせ、語りかけることにより、被告人にとって重要な証拠が不当に軽視されたり、曲解されたりすることを防止することは、弁護人の重要な役割である。本書が、法廷技術の普及を通じて、公正な刑事裁判の実現に少しでも寄与することを願う。
本書の成立について、感謝すべき方々は多い。とりわけ、日本評論社の武田彩さんには、厳しいスケジュールの中で、執筆が遅れがちな筆者らを叱咤激励しつづけ、細かな編集作業をしていただいた。イラストレーターの高橋千史さんには、われわれの意図を端的に表現するオリジナル・イラストを作っていただいた。心より感謝申し上げたい。
2018年1月
高野 隆
河津博史
第1章 法廷での立ち居振舞い
法廷における刑事弁護人の仕事は、依頼人である被告人の隣に座っているだけではない。われわれは立ち上がって発言しなければならない。ときには法廷の中を動き回らなければならない。われわれの発言や動きはすべて依頼人のために行われるものであり、それ以外の目的はない。しかし、依頼人の運命を決めるのはわれわれではない。事実認定者すなわち裁判官と裁判員である1)。事実認定は証拠によって行われる。しかし、証拠は真空の闇の中から飛び出すわけではない。われわれが準備しわれわれが法廷で提供しなければならない。法廷におけるわれわれの仕事は、われわれの発言や動きを通じて、事実認定者をこちらに同調させて、われわれが目標とする依頼人に有利な判決を獲得することである。事実認定者はわれわれの立ち居振舞いを見て聞いて、われわれの依頼人の運命を決める。われわれのケース・セオリーを受け入れてもらうために、われわれは信頼できる情報源でなければならない。事実認定者は、常にわれわれの立ち居振舞いを観察して、われわれの信頼性を吟味している。われわれは、常にそのことを意識する必要がある。
次章以下で公判の各手続における技術を論じることにするが、それらはいずれも立ち居振舞いの技術という側面がある。ここでは法廷とその周辺におけるわれわれの立ち居振舞い方の基本を述べることにしよう。
▼続きは本書でご覧ください!
目次
第2版 はしがき
初版 はしがき
第1章 法廷での立ち居振舞い
Ⅰ 事実認定者への態度
Ⅱ 検察官に対する態度
Ⅲ 被害者参加人に対する態度
Ⅳ 依頼人に対する態度
Ⅴ 感情のコントロール
Ⅵ 服装
Ⅶ 姿勢・動き・音声
Ⅷ 語り
Ⅸ 記録
第2章 ケース・セオリーとケース・ストーリー
Ⅰ ケース・セオリー
Ⅱ 事実認定者の意思決定
Ⅲ ケース・ストーリー
Ⅳ ケース・ストーリーの作り方
Ⅴ TT法
Ⅵ テーマ
第3章 冒頭手続
Ⅰ 冒頭手続の目的
Ⅱ 人定質問から被告人の意見陳述まで
Ⅲ 弁護人の意見陳述
第4章 冒頭陳述
Ⅰ 冒頭陳述とは何か
Ⅱ 何を語るか
Ⅲ どう語るか
〔サンプル〕
第5章 主尋問
Ⅰ 主尋問の目的
Ⅱ 証人の選択と順序
Ⅲ 主尋問の構成
Ⅳ どう訊くか
Ⅴ 尋問メモ、リハーサルなど
第6章 被告人質問
Ⅰ はじめに
Ⅱ するか、しないか
Ⅲ 反対尋問対策
Ⅳ 検察官、裁判官からの被告人質問要求にどう対処するか
第7章 証拠を採用させるための尋問
Ⅰ 証拠の同一性・真正を証明するための尋問
Ⅱ 証拠書類を伝聞例外として採用するための尋問
Ⅲ 証拠の内容を説明するための尋問
第8章 記憶喚起のための尋問
Ⅰ 記憶喚起とは何か
Ⅱ 誘導
Ⅲ 呈示
第9章 反対尋問
Ⅰ 反対尋問の目的
Ⅱ 効果的な反対尋問の構造:SFEの法則
Ⅲ 反対尋問の構成
Ⅳ スタイル:基礎ルール
Ⅴ スタイル:応用ルール
Ⅵ 準備と本番
第10章 弾劾尋問
Ⅰ 弾劾尋問とは何か
Ⅱ 偏見、利害関係、動機
Ⅲ 前科・前歴・非行
Ⅳ 相反する事実
Ⅴ 文献
Ⅵ 自己矛盾供述
第11章 再主尋問
Ⅰ 再主尋問の目的
Ⅱ 質問の事項と方法
Ⅲ 再主尋問の効果と判断
第12章 専門家尋問
Ⅰ 専門家証人とは何か
Ⅱ 主尋問
Ⅲ 反対尋問
第13章 異議
Ⅰ 異議の目的と準備
Ⅱ 異議申立ての判断
Ⅲ 異議申立ての方法
Ⅳ 事実認定者の質問に対する異議申立て
Ⅴ 被害者参加人の質問に対する異議
Ⅵ 冒頭陳述及び論告に対する異議申立て
Ⅶ 異議を申し立てられたときの対応
第14章 最終弁論
Ⅰ 最終弁論の目的
Ⅱ 語るべきこと
Ⅲ 構成
Ⅳ 語り方
Ⅴ ビジュアル・エイド
Ⅵ 書面の配布
〔サンプル弁論〕
第15章 最終陳述
Ⅰ 最終陳述の目的
Ⅱ 最終陳述の内容と方法
巻末付録1
巻末付録2
索引
著者紹介
書誌情報など
-
-
- 『刑事法廷弁護技術[第2版]』
- 著者:高野隆・河津博史
- 紙の書籍
-
定価:税込 3,850円(本体価格 3,500円)
- 発刊年月:2024年7月
- ISBN:978-4-535-52796-6
- 判型:A5判
- ページ数:396ページ
-
-
脚注
| 1. | ↑ | 裁判官と裁判員は、事実認定の他に法令の適用も刑の量定も行う(裁判員法6条1項)。裁判官はその他に法令の解釈や訴訟手続に関する判断を行う(同条2項)。したがって、彼らを「事実認定者」と呼ぶのは正確ではない。とりわけ、有罪無罪の認定手続と量刑審理が分離されておらず、1個の公判ですべてが行われる、わが国の特殊な公判手続を考えると、「事実認定者」というのはミスリーディングですらある。しかしながら、本書の叙述は主として事実関係が争われる事件における法廷弁護活動を念頭においており、他に適切な表現も見当たらないので、慣例に従い「事実認定者」と呼ぶことにする。 |