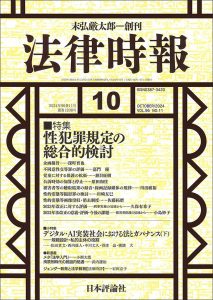ジェンダー教育と法学教育(石田京子)
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」96巻11号(2024年10月号)に掲載されているものです。◆
1 「こんなだったんだね」と「今もこんなだよね」
私が法学部とロースクールの両方で担当している「ジェンダーと法」の授業で、今学期は男女問わず学生から、「朝ドラを取り上げてください!」という声がことのほか多かった。女性初の弁護士、三淵嘉子氏をモデルとした今期のNHKの朝ドラ『虎に翼』は、若い世代の関心も高いようだ。明治26(1893)年に定められた旧々弁護士法は、弁護士資格を得る条件として、「成年男子タルコト」を掲げていたが、これが昭和8(1933)年旧弁護士法により「成年者タルコト」と改められ、女性にも弁護士になる道が拓かれた。このドラマが戦前から戦後という、学生たちからしたら歴史で学ぶような時代を舞台にしながら多くの関心を集めるのは、ドラマに出てくる多くの出来事は「当時はこんなだったんだね」であるにも関わらず、物語の所々に、「今もこんなだよね」が散りばめられているからであろう。
戦後、日本国憲法が制定され、第14条で法の下の平等が謳われた。今日、法制度上の性差別は(ほとんど)存在しないけれども、今なお日本社会の所々で明白なジェンダーギャップがある。ドラマの中で「女性の幸せは良い妻となり良い母となること」と悪意なく当然に考え、主人公の幸せを心の底から願って色々と助言する上司や指導者の言葉や、同じ「弁護士」という資格を持ちながら、女性というだけで仕事の依頼が来ない主人公の姿に、一緒になって理不尽さを感じている学生は少なくないように思う。
2 家庭科教育と女性差別撤廃条約
戦後の初等中等教育においては、多くの教科で男女の区別のない教育が行われてきたが、一部例外が存在した。中学校・高校での家庭科と保健体育である。中学校の技術・家庭科に関して、昭和33(1958)年告示の学習指導要領においては、「生徒の現在および将来の生活が男女によって異なる点のあることを考慮して、『各学年の目標および内容』を男子を対象とするものと女子を対象とするものとに分ける」とされている。高等学校の家庭科についても、昭和45(1970)年告示の学習指導要領において、同様の指針が示されている。当時は、男女で成人後の生活の在り様が異なることが当然に想定されており、女子には調理や被服製作等が、男子には設計・製図や木材加工等が、具体的な教育内容として掲げられていた。その後、昭和52(1977)年の学習指導要領において、このような区別は一部緩和されたが、それでも男女別の履修領域自体の記載は残っていた。