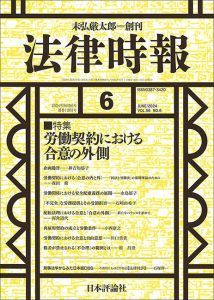(第73回)配転法理と合意の外側について(松井博昭)
 企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。
企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。(毎月中旬更新予定)
両角道代「配転法理における合意と『合意の外側』―新たなバランスを求めて」
法律時報96巻6号(2024年6月号)27~33頁
近時、配転命令に関する最高裁判決があり(最二小判令和6年4月26日労判1308号5頁(滋賀県社会福祉協議会事件))、配転命令の限界について関心が高まっている。両角道代「配転法理における合意と『合意の外側』」(法律時報96巻6号27頁)は、従前の裁判例の法理を整理した上で、「合意の外側」にある何をどれだけ重視するかを考察し、配転の今後の方向性を示す近時の文献として実務上参照価値の高い論稿である。
配転命令権の法的根拠について、学説は、包括的に使用者に委ねられており幅広く認められるとする包括的合意説、個々の労働契約に予定された範囲内で認められるとする労働契約説、使用者の配転命令は認められないとする配転命令権否定説とがあり、通説は、労働契約説を採用するが、就業規則の配転条項を根拠に使用者による包括的な配転命令権が認められるため、実質的には包括的合意説と大きな違いはないとされる。
この点、裁判例は、リーディングケースとされる最二小判昭和61年7月14日労判477号6頁(東亜ペイント事件)において、「Y社は個別的合意なしにXの勤務場所を決定し…転勤を命じて労務の提供を求める権限を有する」(注:Xは労働者、Y社は使用者)と判示し、使用者の包括的な配転命令権を認めた。その上で、最判は、配転命令権の濫用は許されないとしつつも、転勤命令が権利濫用となるのは特別の事情がある場合、すなわち、①業務上の必要性が存しない場合、②他の不当な動機・目的をもってなされた場合、③労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合等に限られるとし、①の業務上の必要性は、余人をもって代え難い等の高度の必要性に限らず、企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは肯定されるとし、③の不利益について、家族(共働きの妻、2歳の娘、老齢の母親)と別居し単身赴任せざるを得ないという家庭生活上の不利益は、通常甘受すべき程度のものであるとして、転勤命令を有効とした。また、かかる判示が転勤以外の配転命令にも広く適用され、配転に関する一般法理として確立したとされる。
本稿は、学説及び裁判例における配転法理について以上のとおり解説した上で、その特徴を解説している。
第一に、配転命令権の有無や範囲については、当事者間に特段の合意がない限り、就業規則の配転条項等に基づいて使用者の包括的な命令権が肯定される。職種や勤務地の限定を認める上では、原則として採用時点における明確な合意が要求され、長期にわたり同じ職種で就労してきたとか、地元で採用され地元で働いてきたという事実だけでは足りない。職種に関しては、医師等の高度専門職は限定が認められることもあるが、アナウンサー、フライトアテンダントのように専門性が高い職種でも否定されることがある。
第二に、権利濫用法理による制約は例外的なものであり、濫用が認められる範囲は狭い。判例上は、配転命令に何らかの合理性があれば業務上の必要性を肯定し、転勤がもたらす生活上の不利益に関しては、病気や障害等をもつ家族の看護・介護に重大な支障をきたすことを労働者が立証した場合に限って権利濫用を認めるという枠組みが定着している。
以上のような判例法理は、「合意の外側」として、定年まで雇用を保障し、解雇を厳格に規制する一方で、配転等に関して企業内の労働調整力について使用者の権限を広く認めるという日本的雇用慣行が色濃く影響したものであるが、本稿は、(コアの部分は維持されているという指摘の存在を認めつつ)現在、雇用の多様化、流動化が進み、日本的雇用慣行は労働契約の解釈において常に参照すべき標準モデルとしての機能は失われていると指摘する。
その上で、現在においては、特定の雇用モデルに重きを置く契約解釈を見直し、合意の内容を丁寧に探究することが求められ、当事者間に職種や勤務地を限定する合意があると認められる場合には、使用者は当該合意に反する配転を命じる権利を有しないとする。前掲最二小判令和6年4月26日も、職種や業務内容を限定する合意がある場合に、使用者は労働者の個別同意なく当該合意に反する配転を命じる権利を有しない旨を判示したものであり、本稿のこの部分の論旨とも一致するものと思われる。また、本稿は、2023年の労基則の改正により、「就業の場所及び従事すべき業務」を労働者に明示することが義務付けられたことに触れつつ、いかなる合意がなされたかは採用時の合意だけではなく、配転命令時の合意を認定するべきであるとも主張する。
以上のような整理を基に、本稿は、労働者の生活上の利益、労働者の職業上の利益について指摘する。
第一に、労働者の生活上の利益について、学説上も、転居を伴う転勤を命じる際に使用者が配慮義務を負うことは広く認められているとし、かかる配慮義務は労働者の生活に大きな影響を与える配転命令全般に及び、その内容は、①労働者への事前説明と事情聴取、②労働者との誠実協議、③それらを踏まえた配転回避努力と不利益軽減措置等であるとする自説を述べる。
第二に、学説においては、「キャリア権」や就労価値論、キャリア配慮義務等、様々な理論構成により労働者の職業的利益に法的保護を及ぼす試みがされているとしつつ、これらは法的拘束力を有する具体的な権利義務として設定するには至っておらず、尊重されるべきものではあるが、生活上の利益と同等の保護を及ぼすべき段階には至っていないとする。
本稿の解説は配転法理のこれまでの経緯を正確に指摘しつつ、「合意の外側」やその変化を意識しつつ、今後のあるべき方向性を指摘するものであり、実務上参考になると思われた。なお、本稿の指摘する今後の方向性は、配転に関する裁量、権限を覊束する方向での指摘であるが、元々、配転命令権が幅広く認められてきた背景には、解雇が容易には認めらないことの影響もある。解雇が必ずしも容易には認められない現状で配転命令権を制約することになれば、使用者の負担が重すぎることにもなりかねず、この点についてどのように調整が図られるかは検討を要すると思われる。
本論考を読むには
・法律時報96巻6号 購入ページへ
・TKCローライブラリー(PDFを提供しています。)
◇この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。
この連載をすべて見る
 松井博昭(まつい・ひろあき)
松井博昭(まつい・ひろあき)AI-EI法律事務所 パートナー 弁護士(日本・NY州)。信州大学特任教授、日本労働法学会員、日中法律家交流協会理事。早稲田大学、ペンシルベニア大学ロースクール 卒業。
『和文・英文対照モデル就業規則 第3版』(中央経済社、2019年)、『アジア進出・撤退の労務』(中央経済社、2017年)の編著者、『コロナの憲法学』(弘文堂、2021年)、『企業労働法実務相談』(商事法務、2019年)、『働き方改革とこれからの時代の労働法 第2版』(商事法務、2021年)の共著者を担当。