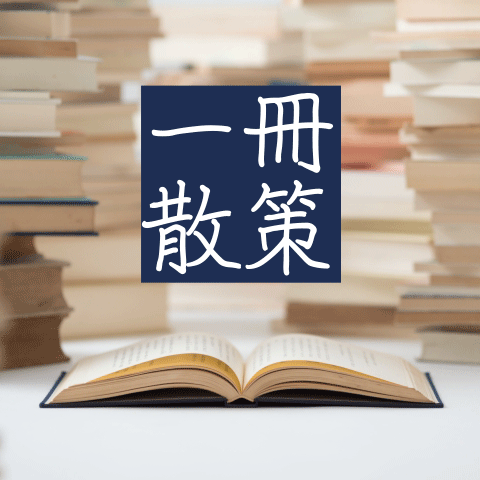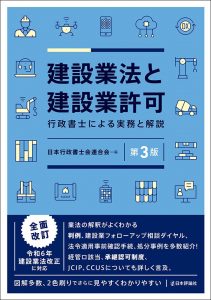『建設業法と建設業許可 第3版—行政書士による実務と解説』(編:日本行政書士会連合会)
ごあいさつ
この度、行政書士を始め、行政機関、建設業関係者など様々な方々にご好評いただいておりました「建設業法と建設業許可」の第3版を刊行することとなりました。
令和2年初頭から世界中で猛威を振るった新型コロナウイルス感染症の流行は、人々の意識や価値観、生活様式や行動に大きな変化をもたらすこととなりました。こうした中、建設業界においても様々な課題が顕在化したことで、社会の変容に対して柔軟に対応しつつ、課題を根本的に見直し、解決することが求められてきております。
特に、過酷な労働環境や高齢化に伴う担い手不足は深刻さを増し、若年層の入職・定着を促進し、人材を確保することは最大かつ喫緊の課題であるといえます。こうした背景を踏まえ、労働者の処遇改善、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止、働き方改革の促進や生産性の向上を目的として、令和6年に建設業法が改正され、持続可能な建設業の実現に向けた解決策の方向性が示されることとなりました。
また、建設業の働き方改革推進の一環として、事務負担を軽減し、生産性の向上を図るとともに、非対面での申請手続を行うことができる環境を整備するため、令和5年1月から建設業許可、経営事項審査電子申請システム(JCIP)の運用が開始されるなど、昨今の建設業界は大きな転換期を迎えています。
行政書士は、これまでも建設業許可申請や経営事項審査申請等の業務を通じて、建設業に関わる皆様のサポートを行ってまいりました。今後におきましても、これら施策の普及・促進、さらには制度に対する国への問題提起や政策提言等、求められる役割はさらに広がり、その存在の重要性は一層増すものと確信しております。
依頼者の信頼に応え、適切な対応をするためには、制度の変遷に応じて最新の知識の習得に努め、研鑽を積まなければなりません。ただ単に許可申請等の手続に係る知識があればよいということではなく、業界全体の施策、展望についても見識を深め、建設業に携わる方々に適切なアドバイスができる存在とならなければならないと考えております。
建設業に関わる皆様の良き相談相手となり、「そうだ、行政書士に相談しよう!」と想起していただき、行政機関からも「行政書士の意見を聞いてみよう!」と思っていただける存在になることこそが、これからの行政書士に求められる役割であり存在意義であると考えます。
本書の改訂にあたっては、改正された建設業法への対応を柱としつつも、建設業許可制度や建設業許可・経営事項審査電子申請システム、建設キャリアアップシステム等についても解説する等、昨今の建設業界を取り巻く話題についても触れております。ぜひ手に取っていただき、日々の業務の参考としていただければ幸甚です。
本書が、初版、第2版と同様に、行政書士はもちろんのこと、行政機関、建設事業者など多くの方々に愛読されることを願っております。
令和7年1月
日本行政書士会連合会
会長 常住 豊
おわりに
前回の改訂から約4年が経過し、第3版を刊行する運びとなった。その間、建設業界は従来からの慢性的な問題が一挙に顕在化し、そこに対応するための多くの政策が次々と施行され、現場は混乱を極めているといっても過言ではない。
新型コロナウイルス、ウクライナ情勢、円安等の影響を受け、資材が高騰し、技術者・技能者不足による労務費の高騰も続いている。令和6年第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)も、こうした状況に対応する内容であることは本書で述べた通りである。
今回の改訂は、章立ての見直しから始まり、全頁を改めるといった方針で取り組んだ。これは現在の状況が4年前と大きく変わっているという背景ももちろんあるが、読者にとってより分かりやすく、より実務的に、建設業法の理解を深めていただくことをモットーに、執筆と編集を進めてきた。処分事例、建設業フォローアップ相談ダイヤル受付状況、法令適用事前確認手続(ノーアクションレター)、意見公募手続(パブリックコメント)における回答といった、実務の場面における行政機関側の考え方が垣間見えるリソースを多く紹介している。さらに、建設業法に関する注目判例も取り上げ、司法の認定や判断を多く紹介することを一つの目標にした。複雑なルールをできるだけ素早く理解できるような図解も、今回多くの時間をかけて作成した。
本書は、建設業法の、特に建設業許可制度について、より実務者の目線で解説している。しっかり読んでいただくことで、今まさに現場で起こっている課題について、建設業に携わる「官」・「民」いずれの立場の皆様にとっても、解決の糸口となれば幸いである。また、全国の行政書士が、本書をきっかけにさらなる研鑽を積み、建設事業者の方々に対して、建設業法の専門家として真のサポートを行い、頼られる存在となることを心から願う。
本書の出版にあたりご尽力いただいた日本評論社ご担当者様、日本行政書士会連合会事務局職員の皆様、そして初版、第2版と執筆や編集にご協力いただいたすべての皆様に、心より感謝したい。
令和7年1月
日本行政書士会連合会
執筆者・編集者一同
目次
ごあいさつ
第1章 建設業許可制度
1 建設業許可制度・種類・区分
(1)建設業許可/(2)軽微な建設工事(法3条1項ただし書、令1条の2、建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】3)/(3)許可の種類/(4)営業所/(5)建設業の種類/(6)一般建設業と特定建設業/(7)許可の有効期間と更新/(8)許可の条件/(9)附帯工事
2 許可基準(経営業務管理責任体制〈経管〉・専任技術者〈専技〉以外)
(1)誠実性/(2)財産的基礎又は金銭的信用(一般許可)/(3)財産的基礎又は金銭的信用(特定許可)/(4)欠格要件/(5)その他
特別編 建設業許可業者が作成する財務諸表の意義
第2章 経営業務管理責任体制(法7条1号)
1 イ該当
2 ロ該当
3 社会保険加入
第3章 営業所技術者(営業所専任技術者)(法7条2号、法15条2号)
1 一般建設業における専任技術者(法7条2号)
2 特定建設業における専任技術者(法15条2号)
第4章 承継認可制度
1 建設業許可の事業承継認可制度等
(1)承継認可制度のメリット/(2)申請先ルール/(3)承継の要件/(4)承継の効果/(5)認可後の手続
2 事業譲渡
(1)会社法上の位置づけ/(2)譲渡譲受/(3)法人成り
3 合併
(1)会社法上の位置づけ/(2)吸収合併/(3)新設合併
4 分割
(1)会社法上の位置づけ/(2)吸収分割/(3)新設分割
5 相続
(1)前提/(2)申請先ルール、承継の要件、承継の効果
6 承継に関わる応用事例
(1)あえて認可制度を利用しない従来手法/(2)株式交換・完全子会社化
第5章 技術者制度と施工技術の確保
1 工事に配置すべき技術者
(1)技術者の趣旨と存在意義/(2)主任技術者/(3)監理技術者/(4)特例監理技術者と監理技術者補佐/(5)特定専門工事における主任技術者の省略/(6)専門技術者/(7)現場代理人
2 配置技術者の職務
(1)具体的な職務/(2)主任技術者から監理技術者への変更/(3)配置技術者の途中交代/(4)専任技術者との関係
3 配置技術者の雇用関係
特別編 出向社員の特例整理
1 通知の整理
2 企業集団制度の出向社員に関する更なる緩和
(1)旧通知/(2)改正への動き/(3)新通知の概要/(4)「3カ月後等配置可能型」のポイント/(5)「即時配置可能型」のポイント
4 現場専任
(1)現場専任ルール/(2)専任の定義/(3)専任を要する期間/(4)現場専任の例外と通知
5 監理技術者資格者証
6 施工体制台帳と施工体系図
(1)民間工事/(2)公共工事/(3)施工体制台帳の内容/(4)施工体系図の内容/(5)再下請通知の内容/(6)作業員名簿の内容
特別編 建設キャリアアップシステム(CCUS)の動き
1 総論
2 国の動き
3 地方の動き
第6章 請負契約
1 請負契約の原則
2 見積り(法20条、法20条の2)
3 請負契約締結
(1)請負契約の内容(法19条1項)/(2)注文書・請書/(3)追加工事の変更契約・追加契約(法19条2項)
4 工期
(1)著しく短い工期の禁止/(2)工期の変更契約
5 請負代金
(1)不当に低い請負代金(法19条の3)/(2)原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代金の設定及び適正な工期の確保(法19条2項、法19条の3、法19条の5)/(3)指値発注(法18条、19条1項、19条の3、20条4項)/(4)不当な使用資材等の購入強制(法19条の4)/(5)やり直し工事(法18条、法19条2項、法19条の3)/(6)赤伝処理(法18条、法19条、法19条の3、法20条4項)
6 支払いと下請負人保護
(1)支払全体/(2)支払保留・支払遅延(法24条の3、法24条の6)/(3)特定建設業者が注文者となった下請契約(法24条の6)/(4)不利益取扱いの禁止(法24条の5)
7 一括下請負の禁止(法22条)
(1)条文整理/(2)原則禁止の趣旨/(3)公共工事と民間工事/(4)一括下請負の具体的定義/(5)実質的関与
8 帳簿
おわりに
判例索引
巻末資料 令和6年建設業法改正関連
執筆者一覧
書誌情報
-
- 『建設業法と建設業許可[第3版]』
- 編著:日本行政書士会連合会
- 定価:税込 3,520円(本体価格 3,200円)
- 発刊年月:2025.01
- ISBN:978-4-535-52828-4
- 判型:A5判
- ページ数:440ページ
- 紙の書籍のご購入
関連情報
◆この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。