優生保護法と憲法学者の自問(棟居快行)
法律時評(法律時報)| 2018.09.26
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」90巻9号(2018年8月号)に掲載されているものです。◆
1 人権論の死角
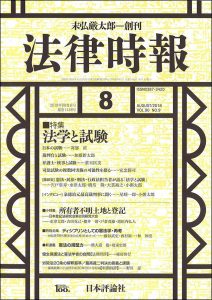 ハンセン病(元)患者の隔離施設の問題は、長きにわたり日本国憲法下でも人権保障の光が及んでいない空間が存在してきたことを日本国民に知らしめた。すなわち、ようやく今世紀になっての2001(平成13)年5月11日、熊本地裁が立法国賠についての全否定的な判例(「在宅投票制判決」=最判昭和60年11月21日民集39巻7号1512頁)をかいくぐる画期的な判決を下し、時の小泉政権が同判決を受け入れて控訴を断念するという決断をしたことにより、世論の知るところとなったのである。遺憾にも私を含む憲法学者の大半は、研究の相当部分を占めるその人権論にもっとも救済を必要とする人々への致命的な死角があることについて、ハンセン訴訟の新聞記事等に接するまで自覚していなかった。もちろん憲法学の本流が、人権保障にはそれが及びうる人的空間的範囲があるというような、特別権力関係論的な視野狭窄に陥っていたとは思わない。むしろ、無意識に他者加害性が強い不治の病という古い医学に基づく俗論を長く引きずり、その真実性を顧みなかった。さらに、いったん第三者との遮断のための閉鎖空間への閉じ込めを人権論として肯定してしまうと、それでは塀の中でどのような人権保障がなされるべきか、というフォローアップを怠っていた。
ハンセン病(元)患者の隔離施設の問題は、長きにわたり日本国憲法下でも人権保障の光が及んでいない空間が存在してきたことを日本国民に知らしめた。すなわち、ようやく今世紀になっての2001(平成13)年5月11日、熊本地裁が立法国賠についての全否定的な判例(「在宅投票制判決」=最判昭和60年11月21日民集39巻7号1512頁)をかいくぐる画期的な判決を下し、時の小泉政権が同判決を受け入れて控訴を断念するという決断をしたことにより、世論の知るところとなったのである。遺憾にも私を含む憲法学者の大半は、研究の相当部分を占めるその人権論にもっとも救済を必要とする人々への致命的な死角があることについて、ハンセン訴訟の新聞記事等に接するまで自覚していなかった。もちろん憲法学の本流が、人権保障にはそれが及びうる人的空間的範囲があるというような、特別権力関係論的な視野狭窄に陥っていたとは思わない。むしろ、無意識に他者加害性が強い不治の病という古い医学に基づく俗論を長く引きずり、その真実性を顧みなかった。さらに、いったん第三者との遮断のための閉鎖空間への閉じ込めを人権論として肯定してしまうと、それでは塀の中でどのような人権保障がなされるべきか、というフォローアップを怠っていた。




