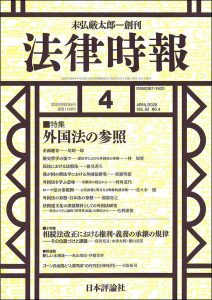ゴーン氏出国と“人質司法”の行方(白取祐司)
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」92巻4号(2020年4月号)に掲載されているものです。◆
1 はじめに
「ゴーン被告、レバノンに逃亡」。2020年1月1日付けの朝日新聞第一面である。日産自動車前会長カルロス・ゴーン氏(以下、「ゴーン氏」)をめぐる一連の騒動は、同氏のレバノンへの国外逃亡(出国)によって、日本の司法界に大きな波紋を呼ぶことになる。
振り返ってみれば、2018年11月19日のゴーン氏逮捕以来、日本の刑事司法は、これまでになく海外からの注目を集めた。より正確にいえば、注目というより、「精密司法」「人質司法」とも表される日本の刑事司法の特異性に対して、ゴーン氏本人の言説も含め、海外メディアから厳しい批判が向けられた。たとえば、フランスの新聞レ・ゼコーは、「日本では、法外な権力をもつ検察官が、訴追のためあらゆる時間と手管を使って被疑者を『参らせ』、無実かもしれない被疑者をも自白に追い込む。それが有罪率99.9%という数字にあらわれている」(2018年12月18日付)と。当初は日本の制度への誤解にもとづく批判もあったが、レ・ゼコーのこの指摘は間違っていない。日本は、21世紀の初頭に始まった司法改革によって、裁判員制度を生み出し(2004年)、全勾留事件の被疑者国選弁護制度(2004年及び2016年)、さらには取調べの録音・録画制度を実現させた(2016年)。しかし、100%に近い有罪率は維持され、弁護人の立会いなく長時間の取調べが行われ、起訴後に保釈制度はあるものの、否認事件における保釈のハードルは非常に高い。これら刑事司法の“日本的”特徴に対する海外からの批判を受けて「人質司法」の見直しへの機運が高まりつつあった。
ところが、昨年末のゴーン氏の国外逃亡で風向きが変わってきた。森雅子法務大臣は、ゴーン氏の発信する日本の刑事司法批判に対して、1月末の国会答弁で、「我が国の刑事司法制度は適正な手続・運用が行われている」と胸を張った。しかし、人質司法という日本の“宿痾”は何も解決していない。ゴーン氏が違法に出国したからといって、われわれに突き付けられた課題から「逃亡」することは許されないはずだ。