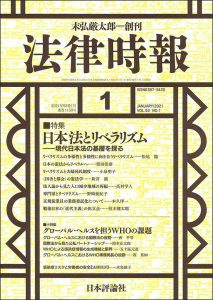感染症リスクと労働者の安全(水島郁子)
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」93巻1号(2021年1月号)に掲載されているものです。◆
1 はじめに
2020年は新型コロナウイルスに翻弄された1年であった。3月24日にオリンピック・パラリンピックの延期が発表されると、4月7日には新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が出された。非日常の始まりであった。全面封鎖がなかった大阪大学のキャンパスも閑散とした。5月半ば、通天閣や各所で大阪モデル達成を示す「緑」のライトアップがなされ、「緑」に光る観覧車に筆者も安堵した。夏に第2波が到来したが、日常を取り戻しつつあった。しかし、冬を前に第3波が到来し、大阪では再度の時短営業が飲食店に要請され、大阪モデル「赤」信号が点灯した。
時短営業や休業によって、どんちゃん騒ぎをする者や泥酔者が少なくなれば、接客対応する労働者の感染リスクの低減が期待できる。時短営業要請は、労働者の安全にも資する。
労働者の安全は、労働者が業務上の危険から保護され、危険が生じた場合には補償が行われることで、守られている。前者は労働安全衛生法(以下「労安衛法」という。)が、後者は労働者災害補償保険法が、中心的役割を担っている。
2 感染症と就業制限
労安衛法68条は、事業者に対して、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものに罹患した労働者の就業を禁止することを定める。同条は、疾病に罹患した労働者の安全を図ることに加え、伝染性の疾病等にあっては事業場の危険を防止し、他の労働者の安全を図ることをねらいとする。新型コロナウイルス感染症は、厚生労働省令に定められておらず、労安衛法に基づく労働者の就業制限は生じない。
新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)6条8項の「指定感染症」に指定された。新型コロナウイルス感染症に罹患した労働者には同法18条が準用され(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令3条)、就業が制限される。すなわち、罹患した労働者(無症状病原体保有者を含む1))は、都道府県知事からの通知により、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務に、病原体を保有しなくなるまでの期間、従事することが禁止される。また、まん延を防止するため必要があると認められるときは、都道府県知事は同法19条および20条の準用により、罹患した者に入院を勧告できる。
感染症法に基づく就業制限は直接労働者になされ、事業者は関与しないが、感染症法に基づく就業制限と入院勧告等により、罹患した労働者の安全と事業場の他の労働者の安全を図るという労安衛法のねらいは事実上達成される。
3 職場における感染防止対策
労安衛法3条1項は、職場における労働者の安全と健康の確保が事業者の責務である、と定める。労働契約法(以下「労契法」という。)5条は使用者の安全配慮義務を定める。職場において新型コロナウイルス感染防止対策を講じることは、事業者・使用者の責務である。もっとも労安衛法は感染症について罹患者の就業制限(前述2)以外の規定を置かず、労契法も安全配慮義務の具体的内容を示していない。そもそも安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種や労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきものである2)。
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議等の知見により、感染リスクを低減する方法が示されている。身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い、3つの密の回避等であり、このような方法をとることにより、ゼロリスクではないものの、職場における労働者の安全が守られる。使用者は、職場の換気を適切に行い、マスクの着用を徹底し、共用部分の消毒を行う等の感染防止対策3)を取ることによって(具体的な対策は各事業場の状況等により異なる)、安全配慮義務(結果回避義務)を遂行することになる。
4 感染症リスクと労働者の出社拒否
職場において感染防止対策がとられても、ゼロリスクではない。新型コロナウイルスの感染リスクを理由に、労働者は出社を拒否できるか。
労安衛法25条は、事業者に、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業から待避させる等必要な措置を講じることを義務づける。同義務は厚生労働省令の定めにより具体化される(同法27条1項参照)4)。同法25条は労働災害発生の急迫した危険があるとき全般に適用されず、労働者は同条を根拠に出社を拒否できない。
労働者が出社するのは、労働契約上労働義務を負うからである。労働者の安全が脅かされる危険がある場合の労働義務について述べた最高裁判例に、日本電信電話公社事件(千代田丸事件)がある5))。最高裁は、軍事上の危険がないとはいえない区域への海底線布設船の出航について、乗組員の本来予想すべき海上作業に伴う危険の類いではなく、危険の度合いが必ずしも大でないとしても、乗組員の意に反して義務の強制を余議なくされるものとは断じ難い、と述べる。この事案での危険は、狙撃、発砲され、撃沈するというもので、新型コロナウイルスの感染リスクとは危険の程度が大きく異なる。
東日本大震災に起因する福島第一原子力発電所事故は、未曾有の災害であった。放射性物質と新型コロナウイルスとの違いはあるが、安全対策が確立しておらず、リスク拡大や健康被害が不明であり、安全に対する不安という点では類似するかもしれない。業務委託契約により役務を提供していたフランス国籍の者が、原発事故の4日後に国外避難し、業務に就かなかった事案(NHK(フランス語担当者)事件)で、東京地裁は、当時、事態は収束の様相を見せておらず、多くの者が不安を感じていたことは公知の事実に属することや、駐日フランス大使館のように自国民に国外等への避難を勧める国も少なくなかったこと等から、当該者が受託していた業務より生命・身体の安全等を優先しても、そのこと自体は強く責められるものではない、とした6)。さらに、当時の状況に照らすと、生命・身体の安全を危惧して国外等への避難を決断した者について、結果的に危険が生じなかったとしても、その態度を無責任であるとして非難することなど到底できないこと、不安の中で職務を全うした者は大きな賞賛をもって報いられるべきであるが、そうした職務に対する過度の忠誠を契約上義務づけることはできない、と述べた。
これらの裁判例から、労働者の生命・身体の安全を脅かす危険がある場合にまで労働者は労働義務を強制されないことが引き出せる。労働義務の限界ともいえ、このような場合、労働者は危険を避ける行動を取ることが許される、と解される。
労働者が労働義務を強制されないのは、どのような場合か。労働者の安全に対する重大な危険がある場合に限られよう。新型コロナウイルスは、飛沫感染や接触感染で感染し、無症状の者から感染する可能性がないとはいえないことから、職場や通勤時の感染リスクを怖れる労働者はいるであろう。しかし、感染リスクへの不安をもって、出社拒否はできない。
労働者の中には、基礎疾患を有する等、感染リスクが高い者もいる。個別の判断となるが、労働義務を強制されない場合もあると考える。もっとも、使用者は安全配慮義務(前述3)を負うので出社拒否以前に、これらの者の感染リスクを低減する方法、たとえば時差出勤や通勤手段の変更、在宅勤務を許容するといった方法を個別に検討するであろう。仮に、使用者が適切な対策を何らとらず、感染リスクが高い労働者に漫然と出社を求めるならば、当該労働者は労働義務を強制されないことにもなろう。
労働者は労働契約上労働義務を負い、出社拒否は労働義務違反を構成する。前述の裁判例は義務が強制されないと述べるにとどまり、義務の消滅や出社拒否の権利を明言していない。そもそもこれらの裁判例は、出航拒否等を理由とする解雇や、職務放棄等を理由とする契約解除の有効性が争われたものであり、その点についてはいずれも無効と判断されている。
5 労働者の感染と労災補償
労働者が疾病に罹患し、それが業務に起因する場合には、労災補償(労災保険給付)の対象となる。業務上の疾病については、一定の業務に従事している者が当該業務に起因して罹患することが医学的な経験則から認められる疾病(職業病)が、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられ、当該職務に従事していた労働者が該当疾病に罹患した場合には、特段の反証がないかぎり、業務起因性が推定される。
新型コロナウイルス感染症は、別表第1の2の「六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病」にあたり、医療従事者等は「1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」にあたりうる。新型コロナウイルス感染症患者の治療や看護にあたる医療従事者の感染は1号に該当し、特段の事情がないかぎり業務起因性が推定され、労災補償の対象となる。それ以外は、「5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」となりうるが、同号には業務起因性の推定が及ばず、労働者側が「業務に起因することの明らかな疾病」であることを個別に立証しなければならない。
新型コロナウイルス感染症は、感染経路が特定されないケースもあり、業務起因性の立証は容易でない。厚生労働省は、当分の間、同号につき、「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とする」との通達7)を発した。
国内事例についての取扱いは、以下のとおりである。まず、①医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合は、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる。感染経路が特定されなくとも、医療業務等に従事し、業務外で感染したことが明らかでなければ、労災保険給付の対象となる。②医療従事者等以外の労働者で感染経路が特定された場合は、感染源が業務に内在していたことが明らかな場合は、労災保険給付の対象となる。職場内でクラスターが発生した場合等が該当する。
③それ以外の者については、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下(複数の感染が確認された労働環境下、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下)での業務に従事し、業務により感染した蓋然性が高い場合は、個々の事案に即して業務起因性が判断される。職場内でクラスターが発生しておらず、感染経路が特定されていないが、職場に感染者がいる場合や、日々数十人と接客する小売店販売員やタクシー乗務員の業務が、これにあたりうる。業務上の認定にあたっては、ア)発症前14日間の業務内容(感染リスクが相対的に高いか)、イ)発症前14日間の私生活の状況(私生活における感染のリスクが低いか)、ウ)医学専門家の知見(当該労働者が業務により感染した蓋然性が高いと認められるか)により、判断される8)。③は、従来の判断基準では業務外とされるか、業務上とされるまでに長期間を要したと考えられ、新型コロナウイルス感染症の特性にかんがみての対応といえる。
通勤時の公共交通機関の混雑状況に不安を感じる者もいるであろう。上記通達は、通勤災害の取扱いについて言及していない。従来の判断基準や上記通達の考え方を踏まえれば、通勤災害と認定されるには、感染経路が特定され、かつ、通勤に通常伴う危険が具体化されたと認められることが必要である。公共交通機関クラスターが確認されていない現時点で、一般的な公共交通機関により通勤する労働者の新型コロナウイルス感染症が通勤災害と認定されることは考えにくい。
(みずしま・いくこ 大阪大学教授)
「法律時評」をすべて見る
「法律時報」の記事をすべて見る
本記事掲載の号を読むには
・雑誌購入ページへ
・TKCローライブラリーへ(PDFを提供しています。次号刊行後掲載)
脚注
| 1. | ↑ | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」(令和2年2月3日健感発0203第3号)。 |
| 2. | ↑ | 最三小判昭和59・4・10民集38巻6号557頁。 |
| 3. | ↑ | 具体的な感染防止対策として、厚生労働省が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(令和2年8月7日改訂)が参考になる。https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf(令和2年11月25日最終確認) |
| 4. | ↑ | 放射性物質の遮へい物が破損した場合や同物質が多量にもれた場合等(電離則42条1項)、酸素欠乏危険作業中に酸素欠乏等のおそれが生じたとき(酸欠則14条)等。 |
| 5. | ↑ | 最三小判昭和43・12・24民集22巻13号3050頁。 |
| 6. | ↑ | 東京地判平成27・11・16労判1134号57頁。 |
| 7. | ↑ | 「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」(令和2年4月28日基補発0428第1号)。 |
| 8. | ↑ | 参照、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」(令和2年10月21日追加)。https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf( 令和2 年11月25日最終確認) |