ルッキズムと法(後編)(立石結夏)
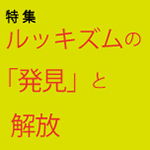 昨今「ルッキズム」という言葉が使われることが多くなりました。ルッキズムとは何なのでしょうか? ルッキズムの何が問題なのでしょうか? 本特集では、まず問題とされるべきルッキズムとは何なのかを考え、そのうえでルッキズムを法的に問題とする場合の議論のありかたを探っていきます。
昨今「ルッキズム」という言葉が使われることが多くなりました。ルッキズムとは何なのでしょうか? ルッキズムの何が問題なのでしょうか? 本特集では、まず問題とされるべきルッキズムとは何なのかを考え、そのうえでルッキズムを法的に問題とする場合の議論のありかたを探っていきます。本稿前編では、ルッキズムがもはや個人の主観やモラルの問題として済ませることができず、法の問題として取り上げるべきであると述べた。
それでは、ルッキズムをどのように法的に整理し、論じていくべきだろうか。
規制すべきルッキズムの類型
ルッキズムの規制は、美しさの否定ではない
前提として、人の美醜についての筆者の考えを先に述べておきたい。
人の外見や姿かたちには、美醜の評価がある。本来その人が持っている外見でも、人工的に作られた外見でも、美しい外見というものが存在する。そして、美しい外見には価値がある。
筆者は美醜の存在そのもの、そして美しさに価値があることは否定しない。そして、自らの意思で自らの外見の美しさを披露したり、より美しくなるための努力をしたり、そのために身体の造形に変更を加えることも否定しないし、あるいは他人の外見の美しさに価値を見出し、親密な関係の中で賞賛の言葉を伝えることも否定しない。
しかしながら、次のような場合には、規制すべきルッキズムだと考える。
差別型ルッキズム
人の外見を理由とした不当な異別取扱いは、異論なく差別である。特に、セクシュアル・ハラスメント、人種差別やいじめ問題は、多くの場合、この差別型ルッキズムを伴う。例えば黒人差別等の人種差別は、差別する側がされる側のIDカードを確認して差別をしているのではなく、外見を見て差別をしている。
審判型ルッキズム
本人が望んでいないのに、あるいは本人の認識や自己評価と無関係に、その本人の外見の美醜を他人が一方的に評価する場面である。
例えば、他人の外見に対する誹謗中傷(「ブス」、「不細工」、「デブ」等)はもちろんのこと、特定の組織内の男性・女性の美醜のランキングをする場合(「この部署で一番美人」「クラスでは一番かわいい・かっこいい」)である。
かつてはよく見られた、学校や会社、地域等で外見の美醜のみを評価の対象とする「美人コンテスト」はこれにあたる。すなわち、本人の意思に関わらず、美醜の競争にエントリーしていない者まで美醜の評価の対象となり、一部の者を美しいと評価することで、残部はそれに劣るという間接的な評価を受けることになる。もっとも、商業的に行われているミスコンテストや、モデルのオーディションは、に、美醜の競争に参加したい者のみがエントリーし、自らの外見の評価を他人に求めているのであるから、規制すべきルッキズムとはいえないであろう。
その他の例として、特に女性に対して言われる「仕事はできるが器量は悪い」、望ましくない例として「美人アスリート」「美しすぎる〇〇(多くは職業名)」等の発言がある。これらも本人が美醜の競争に参加したいかどうかと無関係に、他者が勝手に本人の美醜を取り上げ、審判をしているのである。このようなルッキズムの類型を「審判型ルッキズム」と呼ぶことにする。
時折、「女性部下に対して「美人」と言ってもセクハラになるのは理解できない」等という声を聞くことがあるが、このような感覚を抱く人は審判型ルッキズムとして整理した方が理解しやすい可能性がある 。
強制型ルッキズム
外見と呼ばれるものには、ある程度コントロールできる外見(髪型、化粧、服装等)とコントロールできない外見(肌の色、髪の色、目の色、顔のつくり、体形等)がある1)。
このうちコントロールできる外見については、コントロールができるからこそ他者から美の基準を不当に強制されることがある。例えば、校則、就業規則上の服務規律(男性の長髪・ひげの禁止、女性のみの制服等)のうち、団体の自治・秩序維持の必要性・相当性を超えているものがそれにあたる。原則として、どのような外見を美しいと感じるか、またどのような美しさ(服装、髪型等)を選択するかは本人の私的な領域の事柄で、本来的には本人が自己決定の範囲にあるべきである。このような類型のルッキズムは、「強制型ルッキズム」と呼べるであろう。
法的根拠
ルッキズムを規制するその根拠は、憲法に求めることができる。
法の下の平等
差別型ルッキズムは後述する憲法13条(人格権)のほか、憲法14条(法の下の平等)によって保障されるべきである。
すなわち、憲法14条は、人格の価値が全ての人間について平等であり、人種、宗教、性別、職業、社会的身分等の差異に基づいて不利益な待遇を与えられてはならないという大原則を示したものである。そして、誰もが自分の外見を選んで生まれてくることはできない。そういう意味では社会的な身分の問題ともいえるし、肌の色、目の色、髪の色等は人種も大きく関係し、服装は宗教や性別の影響を受けている。したがって、人の外見は、憲法14条1項に列挙された事由と同等に扱うことができ、合理的な根拠のない別異取扱いは法の下の平等に照らして差別である。
人格権・自己決定権
人格権とは、憲法13条に明文はないものの、最高裁判例が、憲法13条から人格権としての個人の名誉の保護の必要性を説いていること等を踏まえ(最大判昭61・6・11民集40巻4号872頁[北方ジャーナル事件])、現在では、憲法13条を根拠とした基本的人権であると広く理解されている。
人格権と外見については、「個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項(たとえば容ぼう、前科など自己に関する情報)は各自が自立的に決定できる自由」であると説かれたり(芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法』〔有斐閣、第7版、2019年〕124頁)、京都府学連事件判決2)が「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」と判示したことを受けて、個人の容ぼうを承諾なく撮影することは憲法13条の趣旨に反すると論じられている(『注釈日本国憲法(2)――――国民の権利及び義務(1)』〔有斐閣、初版、2017年〕129頁)。
そうであれば、外見に基づく差別(差別型ルッキズム)は当然のこと、「容ぼう」「姿態」を他人から一方的に評価されないこと(審判型ルッキズム)、特定のあるべき「容ぼう」を強制されないことも(強制型ルッキズム)、この憲法13条から導かれる人格権、あるいは人格的利益として法律上の保護に値すると考える。
審判型ルッキズムは、人格権を根拠とし、他人から外見について批評されない権利3)の問題として整理できる。すなわち、人は、それぞれまったく異なる外見をしているから、外見は、人が他人を識別する基本的な人格そのものであり、本人にとってのアイデンティティでもある。その外見を、他人から一方的に評価され、ましては批判されることは、人格を軽視し、時には否定する行為である。
そして強制型ルッキズムは人格権のうち、特に自己決定権の問題として整理することができよう。どのような外見を選択するかは個人の人格と結びついており、原則として自由であるべきである。
その他・表現の自由・信教の自由等
強制型ルッキズム(校則、服務規律等)については、化粧やひげが問題となることがあり、表現の自由や信教の自由と対立する場面もある。
さらなる議論へ
ここまで、ルッキズムを法で規制することの必要性を訴え、規制する言動の類型とその法的根拠の整理を試みた。
審判型ルッキズムについては、法によって規制することは厳しすぎると考える向きがあるかもしれない。しかしながら、審判型ルッキズムは、人の成長のプロセスにおいて繰り返し見聞きすることで、人々の心の中を巣食い、内面化され、いつの間にか社会で共有されている美醜の序列と偏見の根源となり、多くの人が自分らしく生きることを阻んでいると思う。そして、ルッキズム被害者は、ルッキズム加害者にもなりうる。外見の美醜を指摘されることによって傷ついた人が、自身の傷を癒すため、あるいは乗り越えるために、美醜のステレオタイプをより強固にした言動に進むこともある。
したがって、筆者はこの審判型ルッキズムを特に規制する必要性が高いと考えており、既存の法律論で解決することが難しいとも感じている。他方、この類型は、法によって人の意識が変われば即効性が高い類型でもある。モラルの問題として解決できないことは、すでにこの社会が証明している。
本邦では法令こそないものの、実は、裁判例にもすでにルッキズムが表れている。社会にある問題はすべからく裁判に上がってくるから、ルッキズムが裁判に表れることは自然なことであるが、裁判所がどうルッキズムに向き合っているかを検証すると、ルッキズムの克服にとって新たな課題が見えてくる。この問題についてはまた別稿に譲ることとする。
「特集 ルッキズムの「発見」と解放」をすべて見る
脚注
| 1. | ↑ | もっとも、美容整形手術等の施術を受ける場合等、コントロールできる外見とそうでない外見の境界線は曖昧である。 |
| 2. | ↑ | 最大判昭44・12・24刑集23巻12号1625頁。 |
| 3. | ↑ | 他人から外見を批評されないことの重要性について補足する。人は、幼少期から自己あるいは他人の外見の評価に触れ、ルッキズムを内面化して育っている。緑川英子「女子中学生の自己体位に対する意識と食行動」(会津短期大学研究年報50巻81頁)は、「普通の体型」の女子高校生が自分の体型を正しく認識できず、その30.9パーセントが「やや肥満」、9.6パーセントが「肥満」と認識し、誤ったダイエットに神経を使っていることを明らかにしている。また、現代の若い世代のルッキズム体験は、ブックレット「私の人権のはなし-私たちにとって「美しさ」とは何か?-」(日本 YWCA日韓ユース・カンファレンス実行委員会)で具体的なエピソードに触れることができる。 幼少期に内面化した意識を大人になってから取り除くことは難しい。ルッキズム加害者も被害者も出現させないために、人は、幼少期から、自分のことであろうと他人のことであろうと、「公然と他人の外見を評価しない」環境で育つべきであり、次の世代のために社会の意識を変えていくことが急務である。 |
弁護士。第一東京弁護士会、新八重洲法律事務所所属。
「セクシュアル・マイノリティQ&A」(共著、2016年、弘文堂)、「セクシュアル・マイノリティと暴力」(法学セミナー2017年10月号)、「『女性らしさ』を争点とするべきか――トランスジェンダーの『パス度』を法律論から考える」(法学セミナー2021年5月号)、『詳解LGBT企業法務』(共著、2021年、青林書院)




