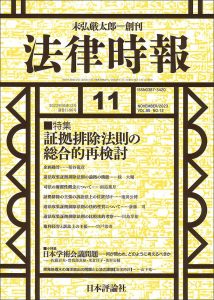(第66回)在宅勤務について──勤務場所の決定及び変更(松井博昭)
 企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。
企業法務、ファイナンス、事業再生、知的財産、危機管理、税務、通商、労働、IT……。さまざまな分野の最前線で活躍する気鋭の弁護士たちが贈る、法律実務家のための研究論文紹介。気鋭の弁護士7名が交代で担当します。(毎月中旬更新予定)
岡本舞子「在宅勤務できるのに出社しなくてはならないのか──勤務場所の決定・変更の法理を問い直す」
法律時報95巻12号(2023年11月号)107-113頁
在宅勤務は、テレワークの一形態であり、コロナ禍において急速に普及が進み、現在も利用されることの多い勤務形態である。岡本舞子「在宅勤務できるのに出社しなくてはならないのか-勤務場所の決定・変更の法理を問い直す」(法律時報95巻12号107頁)は、在宅勤務について、分類、メリット・デメリット、使用者による命令、労働者による請求の是非、合意による実施等、在宅勤務を多角的に検討しており、実務上も参考になると思われた論考である。
本稿は、まず在宅勤務の分類として、コロナ禍において在宅勤務をせざるを得ない緊急時のものと平常時のものがあるとし、平常時のものは、常時在宅勤務と一部在宅勤務に分かれ、一部在宅勤務にも、定期的に継続的に在宅勤務と出社勤務が混在するものと、不定期に必要性や希望に応じて単発的に在宅勤務を実施するものとがあるとする。また、在宅勤務の法的拘束性について、一時的に許容するにすぎない場合と、合意により在宅勤務の運用を固定する場合とがあるとする。
また、在宅勤務について、労働者側のメリットとして、通勤による疲労軽減、仕事と生活の調和が図れること、遠隔地に居住しても就労できること等を挙げ、デメリットとして、コミュニケーション不足の発生、円滑な業務遂行や職業能力形成への支障、仕事と私生活の区分が曖昧になり、プライバシーの侵害、長時間労働に至る可能性があること等を紹介する。これに対し、使用者側のメリットとして、オフィスにかかる費用の削減、生産性の向上、職場としての魅力向上が挙げられ、デメリットとして、情報セキュリティ対策、健康配慮、労働時間管理等の制度・設備の準備が必要な点を挙げる。
次に、使用者の在宅勤務命令について、本稿は、就業規則上の根拠規定がある場合には、使用者が労働者に在宅勤務を命じることができるとする見解(規定説)と、労働者の個別同意がある場合にのみ実施され得るとする見解(個別同意説)に大別されると紹介し、規定説は、在宅勤務を命じることを「勤務場所の変更」と捉えて配転と同様に解釈し、個別同意説は、労働者の私生活の保護(憲法13条)やプライバシー、私的領域の保護の観点から個別同意が必要と解釈する。裁判例は、例えば、使用者が労働者に対し自宅を事務所として勤務するよう命じた点が問題となった京都地判平成23年7月4日労旬1752号83頁(マガジンプランニング事件)が、恒常的な在宅勤務命令は「私生活に対して影響を与える度合いが強い」ために、「自宅を事務所として使用する場合には、労働者の個別の合意か、就業規則上明確な定めが必要であると解すべきである」と判示しており、規定説のように読める。ただし、本稿の立場としては、労働者へのプライバシーの配慮等から個別同意説が適切であるとしている。
さらに、労働者の在宅勤務請求について、本稿は、労使の自主的判断で導入された在宅勤務制度において労働者に在宅勤務請求が認められていたり、あるいは、在宅勤務での就労が合意されたりしていない限りは認められないとするのが多数であるとし、使用者の了承なしで、労働者の請求により在宅勤務を実現することは困難であるとする。その上で、本稿は、配慮を要する特別な事情を有する労働者もいることを指摘し、妊娠中の軽易業務転換請求(労基法65条3項)、障害者の特性に配慮した措置(障害者雇用促進法36条の2~36条の4)、育児介護を行う労働者への配慮(育児介護法26条)等を挙げている。
また、本稿は、在宅勤務に労働者の個別同意を要するとする個別同意説の立場から、在宅勤務の合意について検討している。すなわち、勤務地限定合意を認めた少数の裁判例が、労働者が場所的制約を積極的に申し出ており、使用者がそれを了承した事案を中心に見られること等から、在宅勤務の合意についても、労働者が在宅勤務に特別の希望を有することを表明していたことを重視すべきであるとする。しかしながら、本稿も触れるとおり、勤務地限定合意を認めた裁判例自体が少なく、これを踏まえると、在宅勤務個別合意を認める裁判例も少数になるのではないかと予測される。この点、東京地判令和4年11月16日労判1287号52 頁(アイ・ディ・エイチ事件)は、当該事案における事実経過の下、(契約書に記載された就業場所は形式上、本社事務所であったが)労働契約上の実際の就業場所は原則自宅であり、使用者は業務上の必要がある場合に限って、出勤を求めることができると判示しており、在宅勤務についての個別合意を認めたようにも読めるが、当該事案は、面接時に在宅勤務が基本である旨が明示されており、さらに、入社後も実際に出社は初日のほか1日のみで、残りは継続的に在宅勤務がなされたという、かなり特殊な事案であったように思われる。また、本稿も指摘するとおり、緊急時の在宅勤務と平常時の恒常的な在宅勤務は区別されており、ある特定の原因に基づき一時的に在宅勤務が実施されることによって、将来にわたり、恒常的に在宅勤務の運用が固定されることにはならないといえよう。
このように、本稿は在宅勤務というテーマについて、分類、長所短所の分析、使用者からの指示、労働者側からの請求、合意による場合と多角的に分析しており、参考になると思われた。なお、本稿を離れるが、弁護士として使用者側の案件を担当する際には、会社から在宅勤務に起因する管理の難しさについて相談を受けることが多い。例えば、問題社員が職場への出勤を勝手にやめて在宅勤務と称しているが、どのように対応すべきか(対面で注意する機会がないのに処分はできるのか)、職場との関係が悪化した管理職が長大な時間外労働時間を記録しているがどの程度管理すべきか(積極的に介入するべきか、管理職の裁量を重視するべきか)等といった点が問題となり得る。在宅勤務の拡大に伴い、労働者が在社していないため、会社として対面での指導や直接的な管理が難しいという、在宅勤務の性格に起因する問題が発生しつつあると思われる。
本論考を読むには
・法律時報95巻12号 購入ページへ
・TKCローライブラリーへ
◇この記事に関するご意見・ご感想をぜひ、web-nippyo-contact■nippyo.co.jp(■を@に変更してください)までお寄せください。
この連載をすべて見る
 松井博昭(まつい・ひろあき)
松井博昭(まつい・ひろあき)AI-EI法律事務所 パートナー 弁護士(日本・NY州)。信州大学特任教授、日本労働法学会員、日中法律家交流協会理事。早稲田大学、ペンシルベニア大学ロースクール 卒業。
『和文・英文対照モデル就業規則 第3版』(中央経済社、2019年)、『アジア進出・撤退の労務』(中央経済社、2017年)の編著者、『コロナの憲法学』(弘文堂、2021年)、『企業労働法実務相談』(商事法務、2019年)、『働き方改革とこれからの時代の労働法 第2版』(商事法務、2021年)の共著者を担当。