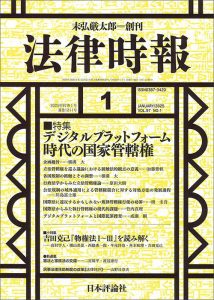民事法律扶助制度の改革(山野目章夫)
 世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。
(毎月下旬更新予定)
◆この記事は「法律時報」97巻1号(2025年1月号)に掲載されているものです。◆
1 1872年の法令
明治政府は、明治5年、芸娼妓解放令を発した。太政官布告第295号である。西暦にすると1872年であり、法令の形式も太政官布告であるから、1889年の憲法制定も1896年・1898年の民法典の編纂も未だ、という時機であることは、いうまでもない。開化期の日本が遭遇した渉外事件やその背景をなす日本の外交的な情勢など事情があったにせよ1)、もちろん内容は正しい。国制や近代諸法典の整備に先駆けての単行法令の制定は、いささかの心地良い驚きすら催す。
けれども、喝采してよい話は、そこまでである。そこまで、というのは、この太政官布告が与える実体的な規律の次元に限っては、という意味にほかならない。
2 ある遊女の運命
遊女かしくは、開化期の明治を生きた一人の女性である。実在の女性であるらしい。日本史の教科書に取り上げられる人物ではないけれども、だからこそ大切ではないか。「遊女いやだ」と叫んだ彼女が役所に赴こうとする2)。でも、いくら法令として芸娼妓解放令が発せられても、その発布の一瞬に世から遊女が消えてなくなるものではない。かしくが役所の門前で遊女は嫌だと叫べばそれで人身の自由が達せられるものでもない。しかるべき役所の窓口を探し当て、公用文の作法にかなう書面を作って出せ、という話は、無理な相談である。抱主らの側とて座視するはずもなく、解放令とは別口の借金の証文を仕立てるなど技巧を用いてくるから、なかなか自由の身にならない日々が続き、「かしくのその後を語る史料は残されていない」3)。100年を超える時を経ても人の苦衷は本質において変わらないものである。私たちは、与えられた運命に懸命に抗おうとした一人の女性の、おそらくは悲しい顛末に一筋の涙を落してもよいのではないか。
3 総合法律支援の課題
おおよそ日本の民法が100年の齢を重ねたころ、先輩のフランスの民法典が200年を迎えた。市民の権利の実現に与る実務職能への旺盛な関心が、同法典の一つの特徴をなす。「日本での継受においてはこの点が最小限にとどめられたために想像がつきにくいが、ナポレオン法典の法は、諸種の実務家の関与なしには成り立たないような体系」を擁する4)。「諸種の実務家」は、彼国はともかく日本にあって、「弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者」にほかならない。これらの人たちは、民法などの実体法制が無関心であるなか、総合法律支援法(同法1条)に登場する。そこでは、民事においての民事法律扶助事業が、そして、刑事についての国選弁護人の選任や国選被害者参加弁護士の選定態勢確保が両翼をなす。
脚注
| 1. | ↑ | 山中至「藝娼妓契約と判例理論の展開」法制史研究41号(1991年)。 |
| 2. | ↑ | 横山百合子『江戸東京の明治維新』(岩波新書、2018年)117-131頁。 |
| 3. | ↑ | 横山・前掲書130頁。 |
| 4. | ↑ | 北村一郎「作品としてのフランス民法典」同編『フランス民法典の200年』(有斐閣、2006年)12頁。 |